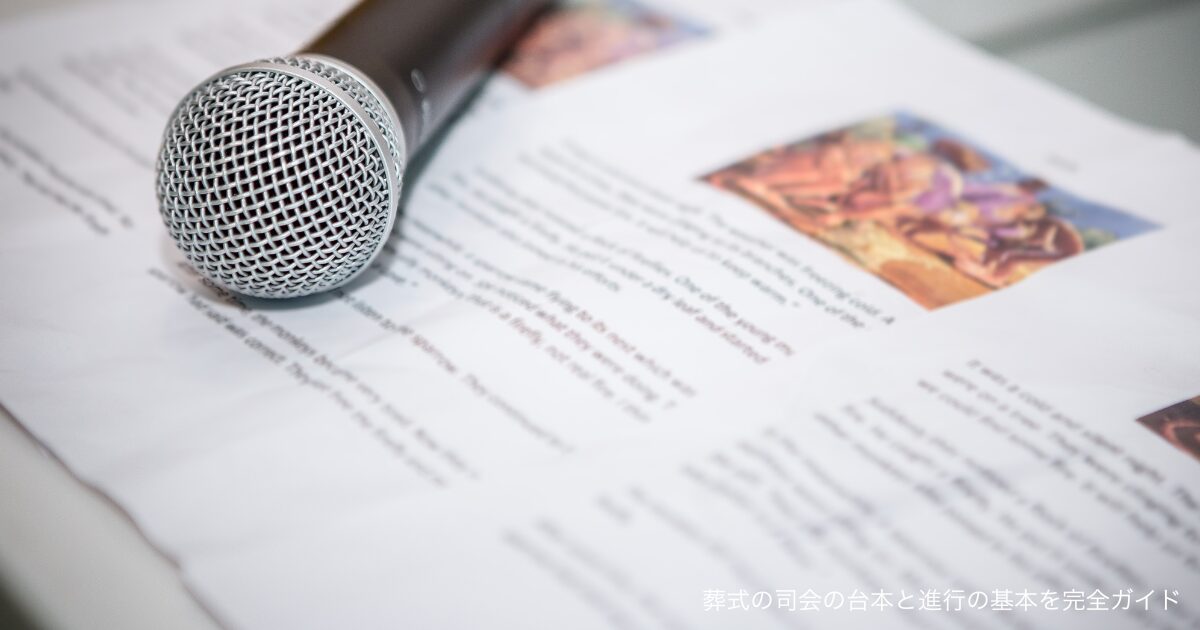葬式の司会を任されたけれど、何をどう話せばよいかわからない。
葬儀という場は人生の中でも特に慎重さが求められる時間です。だからこそ、司会進行に自信が持てないのは当然のことです。
しかし、あらかじめ台本を準備しておけば、必要な場面で必要な言葉を落ち着いて伝えることができます。
本記事では、葬式の司会の台本の基本的な構成から、出だしや締めのナレーション例、進行の注意点までを丁寧に解説しています。
初めて葬儀の司会を担当する方でも、読み進めるうちに「これならできそう」と感じていただける内容になっています。
読みやすく、実践しやすい情報をまとめていますので、どうぞ最後までご覧ください。

台本があると安心感が違いますよ!
【記事のポイント】
- 葬式の司会の台本に必要な基本構成と役割
- 各場面に適したナレーション例と使い方
- 司会進行時の注意点や参列者への配慮方法
葬式の司会の台本

お葬式の司会の台本とは?
お葬式の司会台本とは、葬儀全体の流れを司会者が円滑に進行するために使用する原稿のことです。
一般的な台本には、開式前の案内から読経・弔辞・焼香・閉式に至るまで、式の進行に必要なアナウンス文言が記載されています。これにより、司会が話す内容やタイミングが明確になり、葬儀という厳粛な場にふさわしい進行が可能となります。
この台本の役割は非常に大きく、特に初めて司会を担当する人にとっては心強い支えとなります。葬儀では緊張感や感情の高ぶりから、話す内容を忘れてしまうこともあるため、事前に台本を用意しておくことで、ミスを防ぐ効果も期待できます。
お葬式の司会台本には次のような要素が含まれるのが一般的です。
-
開式前の案内と着席の呼びかけ
-
僧侶や導師の入場の案内
-
弔辞や弔電の紹介文
-
焼香の順序と案内
-
喪主あいさつの紹介
-
閉式・出棺の案内
ただし、台本があるからといって機械的に読み上げるだけでは、式の雰囲気を壊してしまうこともあります。読むスピードや抑揚、そして落ち着いた態度も求められる点に注意が必要です。
また、地域によって風習が異なるため、式場やご遺族の意向を十分に確認し、内容を調整する柔軟さも求められます。
このように、台本は単なる「読む原稿」ではなく、故人と参列者、そして遺族をつなぐ大切な進行ガイドといえます。
葬儀のナレーションの出だしの基本例
葬儀のナレーションにおける「出だし」は、式全体の印象を左右する重要な部分です。
静寂な空間の中で最初に発せられる言葉だからこそ、慎重に選び、遺族や参列者の気持ちに寄り添った表現が求められます。
一般的に、出だしには以下のような基本的な要素が含まれます。
-
式の開式が近いことを知らせる
-
故人への敬意を込めた表現
-
遺族や参列者への感謝の言葉
-
式の流れへの誘導
例えば、「本日は、○○家のご葬儀にご会葬いただき、誠にありがとうございます。まもなく式を開始いたします。どうぞ静かにお待ちください」といった言い回しがよく使われます。
このようなナレーションは、単に情報を伝えるだけでなく、会場の雰囲気を整える効果もあります。参列者にとっても、これから始まる儀式への心の準備ができるため、丁寧で落ち着いた口調が大切です。
ただし、形式にこだわりすぎると、冷たい印象を与えてしまうこともあるため注意が必要です。可能であれば、事前に遺族と打ち合わせを行い、故人の人柄や家族の意向を踏まえた内容に調整すると良いでしょう。
この出だしをスムーズに行えるかどうかで、以降の進行にも大きな差が生まれます。
初めて司会を担当する方は、必ず台本を準備し、練習しておくことをおすすめします。
葬儀の司会は大変とされる理由
葬儀の司会が「大変」とされるのは、単なる進行役ではなく、多くの配慮と判断が求められる責任ある役割だからです。
一見すると台本に従って進めればよいように思えますが、実際にはその場の空気を読みながら臨機応変に対応する力が問われます。
その主な理由として、以下の点が挙げられます。
-
故人や遺族への敬意を欠かさない言葉遣いが必要
-
忌み言葉など使用してはいけない表現がある
-
式の進行が遅れたり乱れたりしないよう調整する必要がある
-
感情に流されず、冷静な対応を維持しなければならない
-
参列者・僧侶・スタッフとの連携も重要
特に注意したいのが「感情のコントロール」です。司会者自身が故人と近しい関係である場合、悲しみの中で言葉を発することになり、冷静さを保つのが困難になることがあります。
また、マイクの使用や発声にも気を配る必要があります。声が小さすぎると聞こえづらく、大きすぎると厳粛な雰囲気を壊してしまうため、場に合ったトーンを維持することが大切です。
このように、葬儀の司会は「読むだけの仕事」ではなく、気配り・話し方・進行管理といった多様なスキルが必要な職務です。
経験が少ない場合は、事前のリハーサルやスタッフとの綿密な打ち合わせを行うことで、当日の負担を大きく減らすことができます。
言い換えれば、準備が十分であればあるほど、「大変さ」は軽減され、安心して司会に臨めるようになります。
葬儀のナレーション集
葬儀のナレーション集は、葬儀司会を務める方にとって非常に役立つ資料です。
形式や言い回しに慣れていない初心者でも、適切な場面で適切な言葉を使えるようサポートしてくれます。ただし、単に読み上げるだけではなく、使い方にはいくつかのコツがあります。
まず、ナレーション集を使用する際は、式の流れや構成を理解した上で、どのタイミングでどの文章を使うかを明確にしておく必要があります。あらかじめ構成を確認しておくことで、慌てずに進行できます。
次に、ナレーション文をそのまま使うのではなく、故人の人柄やご遺族の意向に合わせて微調整することが大切です。画一的な文章は便利ですが、故人への想いを感じさせる内容にすることで、式全体の印象が大きく変わります。
実際に使用する際は、以下のようなステップを意識すると効果的です。
-
式の流れに沿って使用箇所を事前にマークしておく
-
読みにくい漢字や特殊な語句にはふりがなを振る
-
ご遺族との打ち合わせで、使用予定のナレーションを確認しておく
-
読み上げる練習を行い、言い回しや口調を調整しておく
一方で、注意点もあります。ナレーション集を頼りすぎると、会場の空気やタイミングを無視した進行になってしまう恐れがあります。特に、僧侶の読経や参列者の動きに合わせて柔軟に対応できるよう、臨機応変な判断力も求められます。
このように、ナレーション集は便利な反面、丸暗記や機械的な使用では不十分です。読み手としての落ち着いた態度と、場の雰囲気に合わせたアレンジが必要になります。
司会に不慣れな方であっても、丁寧な準備と練習があれば、ナレーション集を活用して安心して進行を任されるようになるでしょう。
葬儀の司会進行の例文
葬儀の司会進行では、式全体を滞りなく導くために、あらかじめ用意された例文に沿って進めることが一般的です。
例文を活用することで、慣れていない人でも適切な言葉遣いと進行が可能になり、葬儀という厳粛な場にふさわしい式が実現できます。
司会進行の例文は、大きく分けて以下の流れに沿って構成されています。
-
開式前の案内(参列者の着席や携帯電話の案内など)
-
僧侶や導師の入場アナウンス
-
開式の宣言と故人紹介
-
弔辞や弔電の紹介
-
焼香の案内と読経の合図
-
喪主あいさつの案内
-
閉式と出棺の案内
たとえば、開式前であれば「まもなく開式となります。ご着席の上、静かにお待ちくださいませ」といった案内が使われます。このような一文があることで、会場全体に一体感が生まれます。
また、弔辞の場面では「ただいまより、故人のご友人でいらっしゃいます〇〇様より、弔辞を頂戴いたします」といった進行例が活用されます。言葉選びの正確さが求められるため、事前に何度か練習しておくと安心です。
さらに、焼香の案内には「これより焼香に入ります。前の方から順にお進みください」といった表現が使われます。式場によっては、案内のタイミングや方法に違いがあるため、現場での打ち合わせが欠かせません。
注意点としては、例文をそのまま読み上げるだけでは不十分な場合があることです。感情を排した冷静な口調を意識しつつも、聞き取りやすく丁寧な言葉で話すよう心がけることが大切です。
さらに、式中にイレギュラーな出来事が起きることもあります。その際に例文に頼りきりでは対応できないため、流れの中で何を伝えるべきかを理解しておく必要があります。
こうして、例文の流れをしっかり把握し、適切なタイミングで適切な言葉を選べるようになると、葬儀司会としての信頼性が大きく高まります。
実践で使える葬式の司会の台本

葬儀の司会での焼香案内の伝え方
焼香の案内は、葬儀の進行の中でも特に緊張感が高まる場面の一つです。
参列者が順番に焼香へ向かうため、会場全体の動きをコントロールする必要があります。適切なタイミングで、わかりやすく、落ち着いたトーンで案内することが求められます。
まず、焼香案内を行う前に、僧侶の読経が始まったことを確認しましょう。多くの葬儀では、読経と同時に焼香が始まります。そのため、読経が始まる直前または直後に、焼香案内のアナウンスを行うのが一般的です。
実際の案内では、次のような表現がよく使われます。
-
「ただいまより、焼香を行います。前方のお席の方より順にお進みください」
-
「焼香のあとは、速やかにご自身のお席へお戻りください」
-
「スタッフの案内に従い、落ち着いてお進みいただきますようお願いいたします」
これらの文言を使うことで、参列者が戸惑うことなく焼香の流れに沿って動けるようになります。
ただし、葬儀の形式や会場の広さ、参列者の人数によっては、もう少し細かい案内が必要になることもあります。例えば、「左側の列から順番に」や「ご高齢の方からご案内いたします」といった補足を入れることで混乱を防ぐことができます。
一方で、急かすような表現や威圧的な言い方は避けるべきです。葬儀はあくまで厳粛な場であり、参列者が故人に手を合わせる大切な時間でもあります。時間の都合があっても、冷静で柔らかな語調を維持しましょう。
また、案内後も、状況を見ながら必要に応じて再案内をすることが重要です。全体の流れを整えるためには、スタッフと密に連携を取り、焼香の動きに遅れや混乱が生じないよう注意を払いましょう。
焼香案内は一見シンプルなようでいて、葬儀全体の印象を左右する繊細な場面でもあります。丁寧な声がけと気配りができると、進行全体が非常にスムーズになります。
弔電披露に使えるナレーション例
弔電の披露は、葬儀の中でも比較的落ち着いたタイミングで行われる進行です。
直接参列できなかった方々からの言葉を故人へ届ける大切な役割があり、司会者のナレーションによってその意味が一層伝わりやすくなります。
披露の前には、まずその意図を簡潔に伝えるアナウンスが必要です。よく使われる冒頭の表現には次のようなものがあります。
-
「ここで、本日お預かりしております弔電を披露させていただきます」
-
「続きまして、故人へ寄せられたお言葉をご紹介いたします」
こうした一言を添えることで、参列者も自然と耳を傾ける体勢になります。
弔電の読み上げでは、差出人の名前と所属、文面の簡潔な紹介が基本です。具体的な披露例としては、
-
「株式会社〇〇 代表取締役 △△様より、心温まるお言葉を頂戴しております。『謹んでお悔やみ申し上げます。○○様のご冥福を心よりお祈り申し上げます』」
といった具合に、文面は短めに抑え、読みやすさを意識すると良いでしょう。
もし弔電の数が多く、すべてを読み上げるのが難しい場合は、その旨を前置きして紹介方法を変えることも可能です。
-
「多数の弔電を頂戴しておりますため、一部ご芳名のみのご紹介とさせていただきます」
こうした案内があれば、披露されなかった差出人の方々にも配慮が行き届いていると伝わります。
披露中は、一定のリズムで、落ち着いた口調を維持することが大切です。特定の文面に感情を込めすぎると、他とのバランスが取れなくなる恐れがあるため、あくまでも中立的に、静かに読み進めましょう。
加えて、弔電の文章はやや硬い表現が多いため、つっかえないよう事前に練習しておくことも忘れてはいけません。読みづらい漢字にはふりがなを付けておくと安心です。
弔電披露は、直接的な弔辞とは異なり、遠方やご高齢の方の気持ちを代弁する場面です。敬意をもって、簡潔かつ丁寧に読み上げることを心がけましょう。
喪主あいさつ前の進行アナウンス
喪主あいさつ前のアナウンスは、式の終盤で行われる重要な案内のひとつです。
式全体の流れを締めくくる喪主の言葉が始まる前に、参列者へ意識を向けさせる役割があります。そのため、場の空気を整えるような落ち着いたアナウンスが求められます。
進行のタイミングとしては、焼香が終わり、僧侶が退場または読経を終えた直後が一般的です。ここで間を空けずにアナウンスを行うことで、式のテンポが途切れることなく続いていきます。
よく使われるアナウンスの例は以下の通りです。
-
「このあと、喪主〇〇様より、ご参列の皆様へごあいさつを頂戴いたします」
-
「それではここで、喪主を代表して〇〇様よりごあいさつをいただきます。どうぞお聞きください」
これらの表現は形式的でありながらも自然であり、参列者に対して礼を欠かすことのない配慮が含まれています。
アナウンスを行う際に注意したいのは、タイミングと語調です。あまりに急いで行うと、会場がざわついた状態のまま喪主あいさつが始まってしまうことがあります。そのため、会場の動きを確認してから、少し落ち着いたタイミングを見計らってアナウンスを行うのが望ましいです。
また、喪主が高齢である、あるいは話すことに慣れていない場合には、声が届きにくいケースもあります。アナウンスの際に「どうぞご静聴ください」と一言添えることで、参列者の注意を促し、聞きやすい環境を作ることができます。
この場面は、参列者が喪主の言葉をしっかりと受け取るための準備時間でもあります。司会者としては、自身の案内がその橋渡しになることを意識し、丁寧で明瞭なアナウンスを心がける必要があります。
葬儀のナレーションの締めの言葉
葬儀におけるナレーションの「締めの言葉」は、式の終わりに相応しい雰囲気を整え、参列者に感謝と案内を伝える大切な役割を持ちます。
この場面では、故人を見送る気持ちを穏やかにまとめると同時に、遺族から参列者へのお礼や、式の終了、出棺、返礼品の案内などを簡潔に伝える必要があります。
よく使用される締めのナレーション例は、次のような表現です。
-
「以上をもちまして、故〇〇様の葬儀ならびに告別式を終了いたします。本日はご多用のところご参列いただき、誠にありがとうございました」
-
「まもなく出棺となります。お見送りをされる方は、そのまま式場にてお待ちください」
-
「お引き物をお忘れのないよう、お帰りの際にお立ち寄りくださいませ」
このように、締めの言葉は感謝と案内の両方を含む内容が基本です。式全体のトーンを崩さないよう、落ち着いた口調と柔らかい表現を意識しましょう。
ただ、注意が必要なのは、感情的になりすぎないことです。葬儀は厳粛な場であるため、ナレーションに過度な感情が込もってしまうと、参列者の集中が乱れる恐れがあります。
また、遺族が最後に挨拶を終えた直後など、式が一区切りついたタイミングでナレーションを挟むことで、より自然な流れを作ることができます。
締めの言葉は単なる「終了の合図」ではなく、参列者をやさしく現実に引き戻すような、静かで丁寧な橋渡しの役割を果たすものです。
司会者としては、葬儀全体を見渡したうえで、会場の状況に合わせて一言添えるなど、柔軟な対応ができると印象が良くなります。
きちんと整った締めのナレーションは、式全体の印象を大きく左右します。最後まで丁寧に、心を込めた案内を心がけましょう。
参列者への配慮を伝える方法
葬儀の司会者には、進行を円滑に行うだけでなく、参列者への細やかな配慮をナレーションの中で自然に伝える役目もあります。
葬儀は静かで緊張感のある場です。参列者は喪失の悲しみの中にあり、会場の雰囲気も非日常的です。こうした状況だからこそ、司会者が適切な言葉で気配りを示すことで、場の空気が和らぎ、参列者が安心して式に臨むことができます。
たとえば、開式前の案内であれば、以下のような表現が効果的です。
-
「本日は足元の悪い中、ご参列いただき誠にありがとうございます」
-
「会場内は足元が滑りやすくなっております。ご移動の際はご注意ください」
また、焼香や移動がある場面では、次のような声かけが参列者への配慮になります。
-
「焼香の際は、前の方から順番にゆっくりとお進みください」
-
「ご高齢の方や小さなお子様をお連れの方は、どうぞご無理のないようお願いいたします」
さらに、長時間の式である場合には、途中で軽く一言添えるだけでも参列者の気持ちが緩和されます。
-
「ご気分が優れない方は、無理をなさらずスタッフにお声がけください」
-
「式中のご体調に不安がある場合は、遠慮なく途中でご退席いただいて構いません」
こうした声かけには、直接的なメリット以上に、「気にかけてもらっている」という安心感を与える効果があります。
ただし、あまりにも頻繁に配慮の言葉を挟むと、式の厳粛さが損なわれてしまう可能性があるため、場面に応じて必要最小限の言葉で伝えることが望ましいです。
参列者全員が気持ちよく、そして丁寧に故人を見送るためには、司会者のこうした小さな気づかいがとても重要です。
あらかじめ会場の構造や参列者の年齢層を把握しておくと、どのような配慮が必要かが明確になります。状況に応じた言葉選びと柔軟な対応力が、質の高い司会進行に欠かせない要素となるでしょう。
まとめ:葬式の司会の台本と実践ポイント

葬式の司会の台本は、葬儀全体を円滑に進行するために欠かせないツールです。
特に初めて司会を担当する人にとっては、台本があることで緊張を和らげ、安心して式を進めることができます。
台本には以下のような内容が含まれるのが一般的です。
- 開式前の案内と着席の呼びかけ
- 僧侶の入場や読経の案内
- 弔辞や弔電の紹介
- 焼香の順序と案内
- 喪主あいさつの紹介
- 閉式や出棺のアナウンス
また、葬儀のナレーションでは「出だし」や「締めの言葉」が特に重要で、式の印象を大きく左右します。
ナレーション集や進行例文を活用すれば、初心者でも落ち着いて対応できる一方で、読み上げるだけでは不十分です。会場の空気を読み取り、故人やご遺族への敬意を込めて語る姿勢が求められます。
焼香や弔電披露の場面では、参列者の動きや心情に配慮した言葉選びが大切です。
このように、葬式の司会台本は「進行の手順書」であると同時に、故人と参列者をつなぐ「心のガイド」でもあります。適切な準備と心配りがあれば、誰でも丁寧で落ち着いた司会進行を行うことができるでしょう。

事前確認、大事ですよ!