葬儀や法事の際、故人の枕元にそっと供えられる白いお団子、枕団子。
皆さんは、この風習に込められた意味や、正しい積み方をご存知でしょうか?
故人が無事にあの世へ旅立てるようにという願いが込められた枕団子は、日本の大切な供養の形の一つです。
しかし、いざ自分が用意するとなると、「何のために供えるの?」「どうやって積むのが正しいの?」と疑問に思う方も少なくないでしょう。
この記事では、枕団子が持つ深い意味から、伝統的な13個の積み方、そして地域による違いや供え方、さらにその後の取り扱いまで、初めての方にも分かりやすく丁寧に解説します。
故人を敬う心を込めて、枕団子を正しく供えるための一助となれば幸いです。
枕団子とは?葬儀・法事における意味を解説

葬式の知恵袋・イメージ
葬儀や法事の際、故人の枕元に供えられる枕団子をご存知でしょうか。
白いお団子がピラミッド状に積まれた姿は、厳粛な雰囲気の中で故人を偲ぶ気持ちを表す、日本の伝統的な風習です。
しかし、なぜ枕団子を供えるのか、どのような意味があるのか、詳しく知らない方も少なくないかもしれません。
ここでは、枕団子が持つ意味や、積み方に込められた思いについて解説します。
枕団子の由来と仏教での意味
枕団子は、故人が無事にあの世へ旅立てるようにとの願いが込められた、旅立ちの供物とされています。
この世での最後の食事、あるいは、あの世への旅路でのお弁当とも言われることがあります。
仏教においては、故人が生前に犯した罪を償い、極楽浄土へ導かれるための「六道(ろくどう)」と呼ばれる道を巡る際に必要な食べ物、という意味合いも含まれているのです。
特にお釈迦様の教えでは、亡くなった方は49日をかけて旅をするとされており、その間のお供えとして重要視されてきました。
地域による枕団子の風習の違い
枕団子は全国的に見られる風習ですが、実は地域によってそのしきたりや形が少しずつ異なります。
例えば、地域によっては団子の数を変えたり、形を少し変えたりすることもあります。
また、枕団子を作る際に特別な粉を使う地域や、団子と一緒に別の供物を添える地域など、細かな違いが見られます。
これは、それぞれの地域の歴史や信仰、あるいは故人を送るための独自の文化が色濃く反映されているためです。
もし心配な場合は、地域の風習に詳しい方や葬儀社に相談してみると良いでしょう。

私も祖父の葬儀で初めて枕団子を目にして、その意味を知り、改めて故人への感謝の気持ちが湧きました。
なぜ13個積むの?個数に込められた意味
枕団子の数は、一般的に13個とされています。
この「13」という数字には、仏教における十三仏(じゅうさんぶつ)信仰が深く関係しています。
十三仏とは、初七日から三十三回忌までのそれぞれの節目を守護する13体の仏様のことです。
故人が旅立つ際に、この十三仏が見守り、導いてくださるという考えから、それぞれの仏様に一つずつ団子を供えるという意味が込められています。
故人が無事に十三の仏様を巡り、最終的に極楽浄土へとたどり着けるように、という遺族の切なる願いが込められているのです。
この13個という数には、故人への深い愛情と、安らかな旅立ちを願う気持ちが凝縮されていると言えるでしょう。
枕団子13個の正しい積み方と配置

葬式の知恵袋・イメージ
枕団子は、故人を敬い、大切に送るためのものです。
だからこそ、その作り方や積み方、配置にも心を込める必要があります。
ここでは、初めての方でも安心して用意できるよう、具体的な方法を解説します。
枕団子作りに必要な材料と準備
枕団子を作るのに特別な材料は必要ありません。
一般的には、以下のものがあれば作ることができます。
- 上新粉(米粉でも可): 故人が食べるものなので、きれいな新しい粉を使いましょう。
- 水: 適量
- 鍋: 団子を茹でるため
- 蒸し器(任意): 蒸す場合は必要
- 盆または三方(さんぼう): 供える際に使用
材料はスーパーマーケットなどで手軽に購入できます。
気持ちを込めて準備することが何よりも大切です。
失敗しない!基本的な枕団子の積み方
枕団子は、白い上新粉を水でこねて丸め、茹でたり蒸したりして作ります。
基本的な作り方は以下の通りです。
- 粉をこねる: 上新粉に少しずつ水を加えながら、耳たぶくらいの柔らかさになるまでよくこねます。
- 丸める: こねた生地を、直径2〜3cmくらいの大きさに丸めます。形は均一になるように意識しましょう。
- 茹でる・蒸す: 沸騰したお湯で茹でるか、蒸し器で蒸します。浮き上がってきて透明感が出たら火が通った合図です。
- 冷ます: 茹で上がったら冷水に取り、冷まします。
さて、最も肝心な積み方ですが、基本はピラミッド状に積みます。
底辺から上に向かって、以下のように積んでいきます。
- 底辺: 5個
- その上: 4個
- その上: 3個
- 一番上: 1個
これで合計13個となります。
不安定にならないよう、丁寧に積み重ねましょう。

最初は崩れてしまわないか心配でしたが、意外としっかり積めました。焦らずゆっくりと作業するのがコツです。
枕飾りの適切な配置場所
枕団子は、故人の枕元に供える「枕飾り」の一部として配置されます。
枕飾りは、故人が亡くなられてから通夜、そして葬儀・告別式までの間に故人の枕元に設けられる祭壇のことです。
具体的には、以下のものが配置されます。
- 枕団子: 故人の最後の食事、旅立ちの供物
- 一膳飯(いちぜんめし): 故人が生前使っていた茶碗にご飯を山盛りによそい、箸を立てたもの
- 水: 故人が喉を潤すため
- 枕花: 故人を慰めるための花
- ローソク・線香: 故人の道しるべとなる灯り
これらの供物を、故人の頭の方に向けて並べます。
枕団子は、故人が安らかに旅立てるよう、心を込めて供えることが大切です。
枕団子に関するよくある疑問と注意点
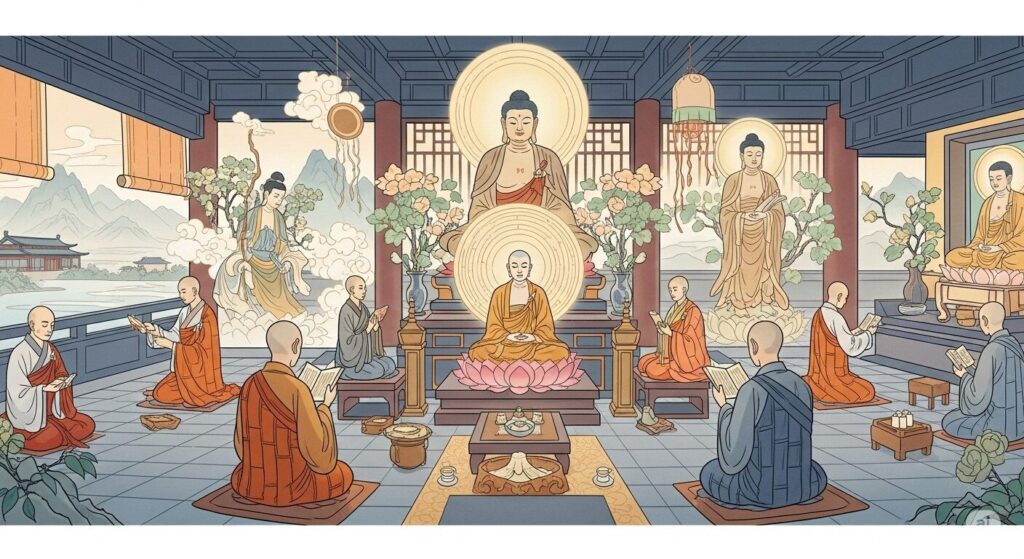
葬式の知恵袋・イメージ
枕団子に関する疑問や、取り扱いに関する注意点について解説します。
適切な対応を知ることで、故人への敬意を表し、遺族も安心して故人を見送ることができます。
枕団子はいつまで飾るべき?
枕団子は、一般的に通夜、そして葬儀・告別式まで飾られます。
葬儀・告別式が終わり、故人が火葬場へ出発する際に、他の枕飾りとともに片付けられるのが一般的です。
地域によっては、四十九日法要まで飾る場合もありますが、それは稀なケースです。
もし、いつまで飾るべきか迷う場合は、葬儀社の担当者や地域の慣習に詳しい方に確認することをおすすめします。
枕団子の処分方法とマナー
枕団子の処分方法は、地域やご家庭によって異なりますが、一般的には以下のいずれかの方法で処分されます。
- 葬儀社に引き取ってもらう: 葬儀終了後、他の供物と一緒に葬儀社が引き取ってくれることが多いです。
- 家族で食べる: 故人の供養として、家族で分けて食べるという地域もあります。ただし、日数が経過したものは傷みやすいので注意が必要です。
- 土に還す: 自然素材でできているため、庭などに埋めて土に還すという方法もあります。
いずれにしても、故人への感謝の気持ちを込めて、丁寧に処分することが大切です。
決して粗末に扱ったり、ゴミとして捨てたりすることのないよう、マナーを守りましょう。

私の実家では、故人への感謝を込めて家族で分け合って食べました。命をいただくことの尊さを改めて感じましたね。
枕団子の代わりに供えるものはある?
現代では、枕団子を準備することが難しい場合や、宗教的な理由などから、別のものを供えることもあります。
枕団子の代わりに供えられるものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 故人が好きだった食べ物や飲み物: 生前、故人が好んで口にしていたものを供えることで、故人を偲ぶ気持ちを表すことができます。
- お菓子や果物: 日持ちがするものや、見栄えの良いものを供えることもあります。
- 造花など: 生花の代わりに、枯れない造花を供える場合もあります。
大切なのは、形式にこだわることよりも、故人を偲ぶ気持ちです。
ご自身の状況や故人への思いに合った方法で、心を込めてお供え物を選びましょう。
まとめ
枕団子は、故人が安らかにあの世へ旅立てるよう願い、残された人々が故人を偲ぶための大切な供物です。
その数や積み方には、仏教の教えや地域の伝統が深く関係しており、一つひとつの団子に故人への深い愛情と敬意が込められています。
もし、あなたが枕団子を準備することになったとしても、今回ご紹介した内容を参考に、心を込めて作っていただければ幸いです。
故人を思う気持ちがあれば、それが何よりも尊い供養となるでしょう。
【関連記事】
【参考資料】

