戦時中の日本では、葬式の行列が当たり前だったのでしょうか?
実際は空襲が続く都市部では葬列すら許されず、身元不明の遺体が仮埋葬されることもありました。
一方で農村部では、地域共同体による協力のもと、簡素ながらも葬儀の形が守られていました。
しかし、そこにも「香典以外は禁止」「火葬か土葬かの選択」など、多くの制約や工夫が存在していたのです。
この記事では、戦時中の都市と農村における葬送の違いや、出征兵士の見送り、遺骨送付の実態までを詳しく解説しています。
今とは異なる厳しい時代の中で、どのように人々が「別れ」と向き合っていたのかを、歴史的資料と具体的な事例から丁寧に紐解いていきます。

歴史を知ると今のありがたみが見えてきますよ!
【記事のポイント】
- 戦時中に葬式が制限された背景
- 都市部と農村部で異なる葬儀の実態
- 香典や供物など葬儀に関する規制内容
戦時中の葬式は行列だった?
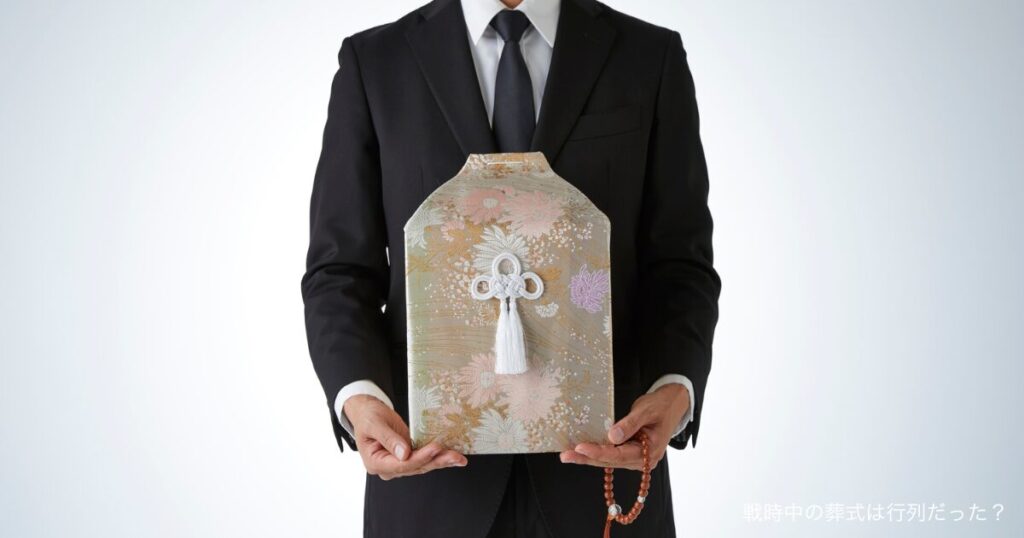
戦時中の都市と農村で異なる葬送事情
戦時中の日本では、都市部と農村部で葬儀のあり方に大きな違いが見られました。
都市部では、空襲や物資不足の影響が顕著で、通常の葬儀を行うことすら困難な状況にありました。 特に大都市では火葬場そのものが被害を受けていたこともあり、身元不明の遺体は仮埋葬として地中に埋める例も多く、遺族が立ち会うことすらできない場合もありました。
一方、農村部では都市ほどの直接的な被害は少なかったため、一定の葬送儀礼を維持することが可能でした。 しかし、ここでも物資統制の影響から葬儀の規模や内容には厳しい制限がありました。
たとえば、以下のような規制が存在していました。
-
酒食や返礼品の提供は禁止
-
香典のみ受け取り可
-
念仏講や寺参りの供物も制限対象
-
親族以外の動員を控えるよう要請
このように、形式的には葬儀が行われていた農村部でも、その中身は大幅に簡略化されていました。
さらに、地方でも結核などの伝染病による死亡者に関しては火葬が義務化されており、通常の土葬とは異なる方法が取られていました。
また、農村では組と呼ばれる地域共同体が葬儀の多くを支え、穴掘りや火葬などの力仕事を担っていたのに対し、都市部では火葬専門職が対応する場面が増え、地域の助け合いが形を変えつつあったことも大きな違いです。
こうして見ると、都市と農村での葬送事情は、物理的な被害の差だけでなく、地域社会の構造や生活基盤の違いによっても、はっきりとした差が生じていたと言えます。
出征兵士の見送りと葬儀の簡素化
戦時中の日本において、出征する兵士を見送る儀式や、戦死した兵士の葬儀は、平時と比べて大幅に簡素化されていました。
理由としては、総力戦体制の中で「贅沢は敵だ」という考え方が浸透し、冠婚葬祭を含むあらゆる儀式の簡略化が国民に強く求められていたためです。
具体的には、出征兵士の見送りに関しても、次のような制限が導入されていました。
-
派手な葬列や音楽の使用は自粛
-
学校や町会からの参加人数を限定
-
式典の時間を短縮
-
飲食の提供は禁止
また、戦死した兵士の葬儀においても同様に、質素で国家への忠誠心を示すような形式が推奨されました。
特に昭和17年頃からは、「出征見送りと葬儀の簡素化」が町会の申し合わせ事項として制度化される地域も増えており、個人の感情よりも「国民全体の士気向上」が優先されていた時代背景がうかがえます。
一方で、農村部の一部では「お国のために亡くなった者」への敬意から、葬儀の簡素化が制度としては求められつつも、実際には地域で立派に送り出そうという動きも見られました。
しかし、それが許されるのはあくまで地域内の評価や人的余裕がある場合であり、物資や労働力が限られる中では難しい選択を迫られた家庭も少なくなかったでしょう。
このように、出征兵士に対する見送りや戦死者の葬儀は、戦時下の国民統制の象徴でもあり、「個人の死」が「国家の戦争努力」に吸収されていく過程を示す一つの表れでした。
戦没者の遺骨送付の実態
戦没者の遺骨が遺族の元に届けられる過程には、戦争の長期化と混乱の中で多くの課題が存在していました。
日清・日露戦争など明治期の戦争では、遺骨の送還は制度としてまだ未整備であり、取り扱いも現在から見ればかなり粗雑なものでした。
たとえば、日露戦争時には、以下のような実態が報告されています。
-
遺骨がタバコの空き箱や新聞紙に包まれていた
-
小包郵便でそのまま遺族宅に届くケースがあった
-
明確な引き渡し手続きが存在せず、自治体任せだった
このような状況に対し、軍内部でも問題意識が芽生え、1904年頃からは改善が図られるようになります。 長野県ではその先駆けとして「遺骨引き渡し式」や「合同葬儀」の制度が整備されました。
その後、戦時体制が強化された昭和期に入ると、戦没者の遺骨は以下のようなルートで運ばれるようになります。
-
前線から補充隊のある県まで運ばれる
-
県庁を経由して市町村へ配達
-
地元の役場職員が遺族へ引き渡す
-
合同葬儀や慰霊式で正式に供養される
しかし、これでも遺骨のすり替えや行方不明といった問題が完全に解決されるわけではありませんでした。 「届いた骨が本当に本人のものなのか」と疑念を抱く遺族も多く、時には空の骨壺だけが戻ってくるという事例すら存在しました。
また、遺骨を運ぶ「届け役」に任命された兵士には、「戦場に戻れば死ぬ」というジンクスがあったため、忌避されがちだったという記録も残っています。
このように、戦没者の遺骨送付は単なる物流ではなく、戦争がもたらした人道的・文化的な問題とも深く結びついていたことを理解する必要があります。
香典と供物に関する制限
戦時中の日本では、物資の統制だけでなく、葬儀に関する慣習にも厳しい制限が加えられました。特に香典や供物に対しては、国の方針として明確な自粛が求められていました。
この背景には、「贅沢を慎むべき戦時下の精神」が強く浸透していたことがあります。地域の町内会や村の集まりでは、冠婚葬祭に関するルールが具体的に申し合わせられ、その中で香典や供物の取り扱いも細かく定められていました。
実際に定められていた主な内容には、以下のようなものがあります。
-
香典は許可されるが、それ以外の金銭的・物質的支援は禁止
-
通夜や葬儀における飲食の提供を全面的に中止
-
念仏講や寺参りの際の供物・お菓子なども禁止
-
法事での贈答品・引き出物も自粛対象
このような措置は、一見すると非常に厳しく思えるかもしれませんが、戦時体制における「公平性の確保」や「無駄の削減」という目的がありました。
一方で、制限には問題点もありました。香典以外を受け取れないというルールは、経済的に余裕のない家庭にとっては実際の助けにならず、逆に遺族の負担が大きくなるケースも少なくなかったのです。
また、供物や返礼品を控えることにより、地域住民同士の関わりが希薄になるなど、精神的な面でのデメリットも生まれました。もともと日本の葬儀には、物を通じて気持ちを表す文化が根付いていたため、それができなくなることで「何もできなかった」という無力感を抱く人もいたようです。
このように、香典と供物に対する制限は物資不足への対応として導入されましたが、その影響は社会的なつながりや精神的な支えにも波及していたことを忘れてはなりません。
特権階級による葬儀の格差も存在
戦時中の日本社会では、建前として「一億一心」「国民平等」が唱えられていましたが、実際には特定の階級に属する人々が多くの面で優遇されていました。葬儀に関しても例外ではなく、明確な格差が存在していたことが記録から確認されています。
具体的には、次のような立場にある人々が「特権階級」として扱われていたとされています。
-
現役および退役の軍人
-
特高警察官や治安維持関連の公務員
-
学校や官庁に勤務する軍属・準軍属
-
その家族や親類縁者
このような人々は、平時の生活においても配給や切符、衣料品の入手などで優先的な扱いを受けており、葬儀においても同様でした。
具体例として、以下のような優遇措置が行われていたとされます。
-
他の家庭では禁止されていた酒食の提供が黙認された
-
通常は省略されていた葬列や見送り行事が実施された
-
より丁寧な形式の葬儀が許可された、または奨励された
-
村や町会からの支援が積極的に行われた
もちろん、こうした対応は公式な制度として明文化されていたわけではありませんが、地域の慣行として黙認されていたのが実情です。
一方、一般庶民の家庭では、上述のような供物の制限、葬儀の簡略化、会場の不足などに直面しており、物理的・精神的な差がより顕著になっていました。
この格差に対して不満を表に出すことは難しい時代でしたが、日記や私信の中には「軍関係の家はやはり違う」といった記述が残されており、当時の人々の心の中に不平等感が広がっていたことがわかります。
いくら「戦時中は国民皆平等」と言われていても、実際には優遇される層とそうでない層が存在し、それが葬儀の場にも表れていたというのが現実でした。これは、戦争がもたらした社会の分断を象徴する一面でもあります。
戦時中の葬式は行列だった?地域ごとの違い

昭和の火葬場が果たした役割
昭和時代に入り、特に戦後を中心に火葬場は葬送の形を大きく変える重要な存在となりました。
この背景には、都市化の進行や埋葬地の不足、衛生観念の変化など、複数の要因があります。特に昭和30年代から50年代にかけては、地方自治体による火葬場の整備が進み、多くの地域で土葬から火葬への移行が加速しました。
火葬場の役割は以下のように整理できます。
-
遺体処理の衛生的な管理
-
葬儀の時間・場所の確保と効率化
-
墓地スペースの有効利用
-
地域住民への心理的安心感の提供
これまで各家庭や集落で行っていた「墓地での火葬」は、環境面・安全面での課題が多くありました。火の管理、煙の問題、そして近隣住民とのトラブルなど、火葬を行うたびに解決しなければならない課題が存在していたのです。
その点、昭和54年に建てられたような本格的な市営火葬場では、これらの問題を一挙に解消しました。近代的な焼却炉や待合施設が整い、地域住民が安心して利用できる環境が整ったことは、大きな転換点でした。
ただし、火葬場が整備されるまでの過渡期には、以下のような問題も見られました。
-
設備が不十分で利用希望者を全て受け入れられない
-
高齢者の中には火葬を「冷たい」扱いだと感じ、土葬を希望する声もあった
-
火葬場が整っても、伝統や宗教的価値観によってすぐには浸透しなかった
これを乗り越えた結果、火葬は今や日本の葬送の標準となっています。
つまり昭和の火葬場は、単なる施設としてではなく、「葬儀文化の近代化」を象徴する存在だったといえるでしょう。
集落ごとの火葬方法と儀礼の差異
日本各地の農村部では、戦前から昭和中期まで、集落ごとに異なる火葬の方法と儀式の作法が根強く残っていました。
これは単なる文化の違いというよりも、地形、信仰、燃料資源の有無、地域共同体のあり方など、さまざまな要素が複雑に絡み合った結果です。
火葬のやり方には、次のような違いが見られました。
-
墓地の一角に設けられた「火屋(ひや)」を使う地域
-
濡れ筵(むしろ)で遺体を包み、藁を燃料にして蒸し焼きにする方法
-
石や木を組んで即席の炉を作り、棺ごと焼く形式
-
座棺(遺体を座らせた状態)で焼く風習があった地域も存在
また、火をつける役割や焼け具合を確認する役割も、集落の中で厳格に分担されていました。
-
喪主や長男が点火する
-
夜間に交代で焼け具合を確認する
-
翌朝に身内だけで骨拾いを行う
このように、葬儀は単に「焼く」だけの行為ではなく、集落全体の協力で成り立っていた儀式でした。
しかし、これらの儀礼には課題もありました。火葬の方法が非効率で、悪天候時には火がつかない、あるいは焼却に時間がかかるといった問題が頻発したのです。また、火を使う作業であるため、火事のリスクも常に抱えていました。
それでも地域ごとに細かく異なる葬送方法が受け継がれてきたことは、住民同士の絆や死者への敬意がいかに大切にされていたかを物語っています。
これらの風習は、のちに火葬場の整備とともに姿を消していきましたが、地域文化としての価値は今なお見直されつつあります。
土葬と火葬が共存した戦時の習慣
戦時中の日本では、土葬と火葬が同時に存在するという、いわば過渡期の葬送文化が見られました。
戦時下という特殊な状況により、すべての葬儀が制度的に統一されることはなく、状況に応じて方法が選ばれていたのです。
土葬が選ばれた主な理由には、以下のようなものがあります。
-
火葬に必要な燃料(藁・炭・薪)が不足していた
-
空襲などの影響で火を使うと目立つため避けられた
-
火葬場が遠く、遺体の移動が困難だった
-
遺言により土葬を希望するケースがあった
また、子どもの遺体については「かわいそうだから焼かない」という感情的な理由で、あえて土葬を選ぶ家庭も存在しました。
一方、結核や疫痢といった感染症による死者は、伝染防止の観点から墓地で火葬されることが義務付けられていました。このとき使われたのも、地域にある仮設の火屋や即席の炉でした。
このような選択の幅があったことで、各家庭や地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となっていたのは確かです。
しかし、土葬と火葬が共存していたことで、次のような問題も発生しました。
-
墓地の管理が煩雑になった
-
墓地が災害で崩れるリスクが増加した
-
衛生面の懸念から住民同士で対立することもあった
昭和40年代以降、これらの問題を受けて市営斎場の整備が進み、火葬が主流となっていきます。
こうして見ると、戦時中の土葬と火葬の共存は、制度や信仰ではなく、現実的な状況判断の中で選ばれていた「生活の選択肢」だったといえるでしょう。
火葬専門職の登場と町場の変化
昭和初期から中期にかけて、都市部や町場を中心に「火葬専門職」が登場したことで、葬送の現場には大きな変化が生まれました。
従来の農村部では、火葬を行うのは地域内の「組」の若者たちであり、住民同士の助け合いの一環として機能していました。穴を掘る人、火を焚く人、焼け具合を確認する人など、それぞれが役割を持ち、共同作業で一晩かけて葬送を行っていたのです。
一方で、町場では人口が密集し、葬儀の件数が増加したことや、地域内のつながりが比較的希薄であったことから、葬儀の一部を専門職に委ねる流れが始まりました。
火葬専門職の登場によって、以下のような変化がもたらされました。
-
地域住民の負担が減り、葬儀の効率が向上した
-
火葬の質が安定し、遺族の不満やトラブルが減少した
-
火葬の時間や段取りが標準化され、葬儀社との連携も進んだ
こうした変化は便利さの反面、「地域のつながりの希薄化」という新たな課題も生みました。農村での葬送は、地域の一体感を強める大切な行事でもありましたが、それが外注されることで、次第に「地域の手を借りる文化」が失われていったのです。
さらに、火葬専門職に頼る地域では、次のような問題も見られました。
-
見舞いとして持参する酒や食べ物が「火葬の質」に影響すると信じられていた
-
火葬業者との関係性によって、対応に差が生じる場合があった
-
焼き場の管理や修繕に関する責任が不明確になることもあった
実際、「見舞いを持っていかないと丁寧に焼いてもらえない」といった不安から、遺族が夜遅くに酒を届けに行くこともありました。
このように、火葬専門職の登場は町場の葬儀を近代化・合理化する一方で、地域共同体の役割を徐々に縮小させるきっかけにもなったのです。
伝染病による火葬義務と背景
明治期から昭和にかけて、日本では結核や疫痢などの伝染病によって多くの人命が失われました。その中で、衛生面から土葬が見直され、特定の病気による死亡者に限って「火葬義務」が定められるようになりました。
この流れを加速させたのが、1897年に施行された「伝染病予防法」です。この法律により、伝染病死者の埋葬について明確なルールが設けられました。
火葬が義務とされた背景には、以下のような事情がありました。
-
遺体からの病原体拡散を防止するため
-
墓地周辺の水質汚染を防ぐため
-
遺体の腐敗による悪臭や害虫発生を防止するため
当時の衛生技術では、病原体の完全除去が難しく、土葬による感染拡大が懸念されていました。
そのため、地域の墓地では次のような火葬対応が取られるようになりました。
-
遺体を棺ごと焼却するための簡易な「火屋(ひや)」を設置
-
濡れ筵(むしろ)と藁を使って蒸し焼きにする方法を採用
-
火葬作業は地域住民(組)の若者たちが一晩かけて行う
火葬義務があるとはいえ、物資が不足していた戦時中には燃料の確保が困難で、火葬そのものが大きな負担になることもありました。喪家が自ら柴や炭を準備する必要があり、経済的余裕のない家庭では周囲の支援に頼ることもありました。
さらに、火葬は夜間に行われることが多く、遺体の焼け具合を確認する作業も住民にとって精神的に大きな負担でした。
一方で、こうした火葬の義務化は、日本人の衛生観念や葬送観を変える契機にもなりました。
-
火葬の方が清潔で安全だという認識が広がった
-
葬送の合理化と公的管理の必要性が再確認された
-
家族や地域の死者に対する接し方が変化していった
このように、伝染病による火葬義務は、単に衛生対策にとどまらず、日本社会全体の葬儀文化に大きな影響を与えた制度だったのです。
まとめ:戦時中の葬式は行列だった?実情と地域差の実態

戦時中の日本では、葬儀の形は大きく変化していました。
都市部では空襲や物資不足の影響で、葬列や儀式の実施自体が困難になることも多く、仮埋葬や無届けの簡素な処理が行われた例もあります。
一方、農村部では比較的日常が保たれていたものの、葬儀は制限され、以下のような対応が取られていました。
- 香典以外の金品や供物は禁止
- 出征兵士の見送りや戦死者の葬儀は簡素化
- 地域の「組」が火葬や穴掘りなどを分担
また、火葬が広がる過程では、衛生面の課題や伝染病への対応から、火葬義務が法的に定められた地域もありました。
さらに、軍関係者などの特権階級には葬儀の形式面で優遇が見られ、一般家庭との間に格差が生まれていたことも記録されています。
このように、戦時中の葬式には、国の方針や地域社会の状況、物資事情が色濃く反映されていたのです。

戦時中は葬列どころじゃなかったようです。
今の平和に感謝したいですね!

