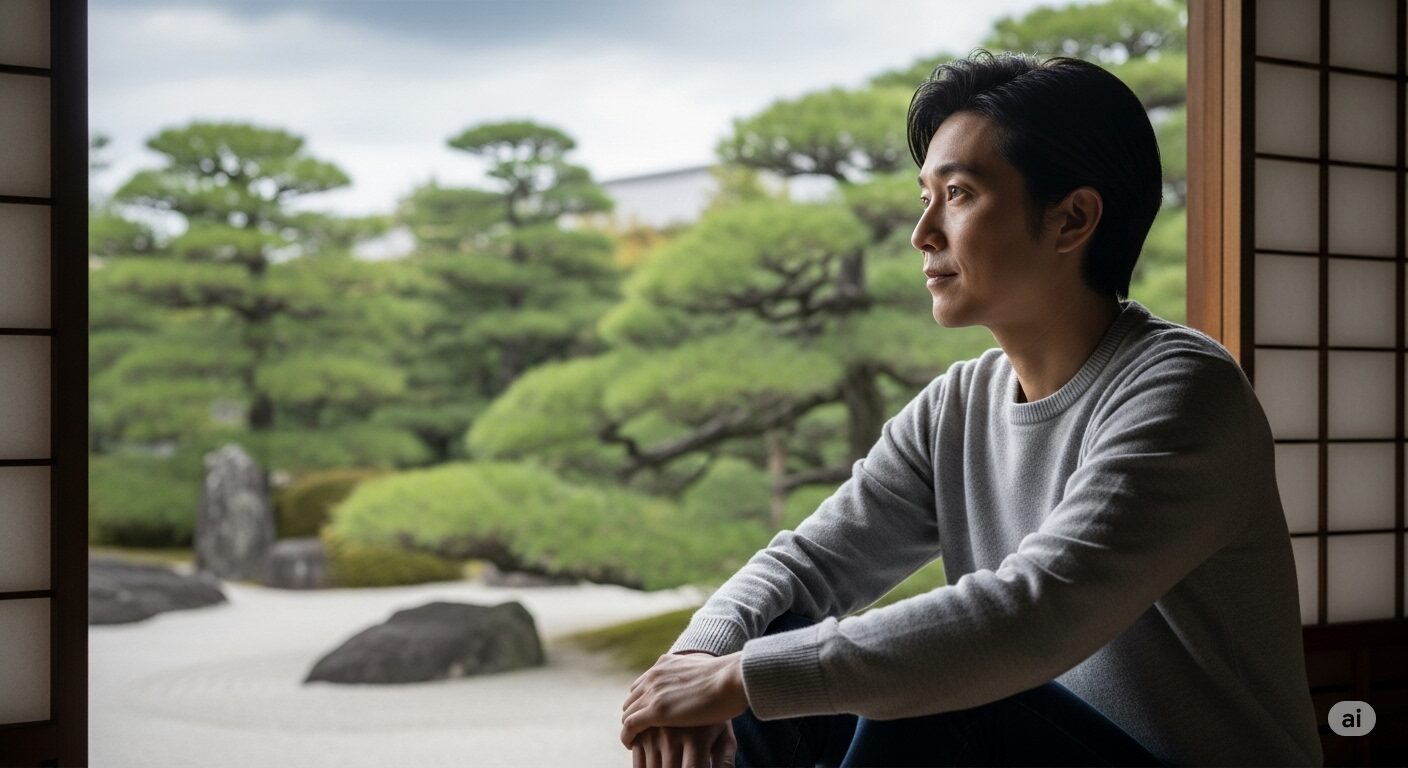突然の身内の不幸。
深い悲しみとともに、考えなければならないのが会社への連絡です。
「なんと言って休めばいいんだろう…」
「『葬式で休みます』でいいのかな?」
「そもそも、こういう時のお休みって正式にはなんて言うの?」
動揺している中では、言葉一つを選ぶのも難しいものですよね。
この記事では、そんなあなたの不安に寄り添い、葬式で会社を休む際の正式な言い方や、知っておくべき言葉の読み方、そして具体的な伝え方まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。
いざという時に慌てず、失礼なく対応できるよう、一緒に確認していきましょう。
葬式休みの正式な言い方は「忌引(きびき)休暇」

葬式の知恵袋・イメージ
まず、結論からお伝えします。
葬儀で会社を休むことは、一般的に「忌引(きびき)休暇」と言います。
「葬式休み」という言い方が間違っているわけではありませんが、ビジネスシーンや公的な場では「忌引」という言葉を使うのが社会人としてのマナーです。
「忌引」の正しい読み方は「きびき」
この「忌引」という漢字、意外と読み方に迷う方が多いのではないでしょうか。
正しくは「きびき」と読みます。
「いんびき」や「きいん」などと読み間違えやすい言葉ですが、この機会にぜひ覚えておきましょう。

言葉の意味を知ると、ただの休暇ではないと気持ちが引き締まりますよね。故人を想う大切な時間なのだと改めて感じます。
「忌引(きびき)」の意味とは?言葉の由来
では、「忌引」とは、そもそもどのような意味が込められているのでしょうか。
漢字を分解してみると、その深い意味が見えてきます。
- 忌(いみ):死者に対する慎み、けがれを避けること。
- 引(ひき):身を引く、その場から退くこと。
つまり「忌引」とは、「近親者の死に際して、社会的な活動を一時的に休み、悲しみを乗り越え、心身を慎むこと」を意味する、非常に敬意のこもった言葉なのです。
単に葬儀に参列するためだけの休みではなく、故人を悼み、喪に服すための大切な期間であることを示しています。
「忌引き」と「忌引休暇」の違いは?
よく「忌引き」と「忌引休暇」という二つの言葉が使われますが、厳密には少しニュアンスが異なります。
- 忌引き:喪に服すという「行為そのもの」を指します。
- 忌引休暇:忌引きのために会社から与えられる「休暇制度」を指します。
会話の中ではどちらを使っても意味は通じますが、会社に休暇を申請するという文脈では「忌引休暇を取得します」と伝えるのがより正確な表現と言えるでしょう。
忌引と合わせて知っておきたい言葉と読み方
忌引の連絡をする際には、他にもいくつか知っておくとスムーズに話が進む言葉があります。
特に読み間違えやすい言葉をピックアップしましたので、この機会に確認しておきましょう。
| 言葉 | 読み方 | 意味と使い方 |
| 続柄 | つづきがら | 亡くなった方と自分との関係性のこと。(例:父、母方の祖母) |
| 弔事 | ちょうじ | 葬儀などのお悔やみごと全般のこと。(対義語:慶事) |
| 慶弔休暇 | けいちょうきゅうか | 結婚(慶事)や葬儀(弔事)の際に取得できる休暇制度のこと。 |
| 逝去 | せいきょ | 「死去」の尊敬語。身内以外の方、特に目上の方の死に用いる。 |
誰の葬儀かを伝える「続柄(つづきがら)」
「続柄」は「ぞくがら」と読み間違えやすいので注意が必要です。
会社に連絡する際は、「誰の」葬儀のために休むのかを明確に伝える必要があります。
なぜなら、一般的に会社が定める忌引休暇の日数は、この続柄によって変わってくるからです。
葬儀などのお悔やみごとを指す「弔事(ちょうじ)」
「弔事(ちょうじ)」は、人の死を悼む出来事全般を指す言葉です。
反対に、結婚や出産などのお祝い事は「慶事(けいじ)」と言います。
この二つを覚えておくと、次の「慶弔休暇」の理解が深まります。
休暇制度の名称「慶弔(けいちょう)休暇」
多くの会社では、福利厚生の一つとして「慶弔休暇」の制度が設けられています。
これは、慶事と弔事があった際に取得できる特別な休暇のことです。
忌引休暇は、この慶弔休暇の中の「弔事における休暇」に該当します。
亡くなったことを伝える際の「逝去(せいきょ)」と「死去」の違い
「逝去」は尊敬語です。
上司や取引先の方など、社外の第三者に身内の死を伝える際は「父が死去いたしました」というように「死去」を使います。
一方で、他社の人の訃報に触れる際は「〇〇様がご逝去されたと伺いました」のように「逝去」を使い分けるのがマナーです。
【状況別】忌引休暇を取得する際の伝え方・言い方

葬式の知恵袋・イメージ
言葉の意味がわかったところで、いよいよ実践です。
実際にどのように会社へ連絡すればよいか、電話とメールのパターンに分けて例文をご紹介します。

私も初めての時、電話口で声が震えました。伝えるべき要点だけでもメモに書き出しておくと、少し落ち着いて話せますよ。
電話で伝える場合の例文
基本は、直属の上司へ電話で直接伝えるのが最も丁寧な方法です。
あなた:「お疲れ様です。〇〇です。今、お時間よろしいでしょうか。」
上司:「お疲れ様。大丈夫だよ、どうした?」
あなた:「私事で大変恐縮なのですが、昨夜、父が亡くなりました。つきましては、忌引休暇をいただきたく、ご連絡いたしました。」
上司:「そうか…、それは大変だったな。お悔やみ申し上げます。休暇の件、承知したよ。」
あなた:「ありがとうございます。葬儀の日程が確定しましたら、改めてご連絡いたしますが、ひとまず本日より3日間お休みをいただいてもよろしいでしょうか。」
上司:「わかった。手続きのことは総務にも確認しておくよ。仕事のことは気にしなくていいから、最後のお別れをしっかりしてきなさい。」
あなた:「ご配慮いただき、ありがとうございます。担当しております〇〇の件は、△△さんに引き継ぎをお願いしております。緊急の場合は、私の携帯にご連絡いただければと存じます。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。」
伝えるべきポイント
- 誰が亡くなったか(続柄)
- 忌引休暇を取得したい旨
- 休みたい期間(現時点でわかる範囲で)
- 仕事の引き継ぎについて
- 休暇中の連絡先
メールで伝える場合の例文
上司が不在の場合や、深夜・早朝で電話ができない場合は、まずメールで一報を入れましょう。
その後、改めて電話で連絡するのが丁寧な流れです。
件名:【忌引のご連絡】〇〇部 〇〇(自分の名前)
本文:
〇〇部長
お疲れ様です。
〇〇部の〇〇です。
私事で大変恐縮ですが、本日未明に祖母が亡くなりました。
つきましては、下記の通り忌引休暇を申請させていただきたく存じます。
■続柄:祖母
■休暇期間:〇月〇日(〇)~〇月〇日(〇)の〇日間
■休暇中の連絡先:090-XXXX-XXXX
葬儀の日程など詳細が確定いたしましたら、改めてご報告いたします。
休暇中、ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
〇〇部 〇〇 〇〇
続柄をどう伝える?言い方の具体例
会社への報告では、自分との関係性を簡潔に伝えることが大切です。
| 亡くなった方 | 伝え方の例 |
| 実の父・母 | 「父」「母」 |
| 配偶者の父・母 | 「妻の父」「夫の母」または「義父(ぎふ)」「義母(ぎぼ)」 |
| 兄弟・姉妹 | 「兄」「姉」「弟」「妹」 |
| 祖父・祖母 | 「祖父」「祖母」(父方か母方か伝えるのがより親切) |
| 配偶者 | 「妻」「夫」 |
| 子 | 「長男」「長女」など |
忌引休暇に関するよくある質問

葬式の知恵袋・イメージ
最後に、忌引に関して多くの人が抱く疑問にお答えします。
Q. なぜ「葬式休み」ではなく「忌引」と言う方が良いのか
A. 心情と敬意の問題です。
「葬式休み」は少し直接的で、人によっては軽い印象や事務的な響きに聞こえてしまう可能性があります。
一方で「忌引」という言葉には、前述の通り「故人を悼み、慎む」という深い意味が込められています。
この言葉を選ぶこと自体が、故人への敬意、そして社会的な配慮を示すことに繋がるのです。
Q. 忌引休暇の日数と続柄の関係は?
A. 会社の就業規則によって定められています。
忌引休暇は法律で定められた休暇ではないため、日数や対象となる続柄の範囲は、会社ごとの就業規則で決められています。
一般的な日数の目安は以下の通りですが、必ずご自身の会社の就業規則を確認してください。
| 続柄 | 忌引休暇の日数(目安) |
| 配偶者 | 10日間 |
| 実父母 | 7日間 |
| 子 | 5日間 |
| 兄弟姉妹 | 3日間 |
| 祖父母 | 3日間 |
| 配偶者の父母 | 3日間 |

遠方での葬儀の場合、移動日を考慮してくれる会社もあります。まずは上司に正直に状況を相談することが大切ですよ。
Q. 忌引の連絡はいつまでにすべき?
A. 不幸がわかった時点ですぐに連絡するのが原則です。
たとえ深夜や早朝であっても、まずはメールで一報を入れるなど、できるだけ早く連絡しましょう。
無断欠勤の状態になることだけは絶対に避けなければなりません。
まずは「第一報」を入れ、詳しいことが分かり次第「第二報」を入れる、というように段階的に報告すれば問題ありません。
まとめ

葬式の知恵袋・イメージ
今回は、葬式で会社を休む際の正式な言い方である「忌引(きびき)」について、その読み方や意味、そして具体的な伝え方を解説しました。
- 葬式で休むことは「忌引(きびき)休暇」と言うのがマナー
- 「忌引」には「故人を悼み、慎む」という深い意味が込められている
- 連絡は「分かった時点ですぐに」「直属の上司へ電話」が基本
- 伝える際は「続柄」と「休む期間」を明確に
突然のことで動揺する中、冷静に、そして誠実に対応することは簡単なことではありません。
しかし、「忌引」という言葉に込められた意味を心に留めておけば、きっとあなたの行動や言葉に、故人を悼む気持ちと周囲への感謝が自然と表れるはずです。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげる一助となれば幸いです。
まずはご自身の心を休め、大切な方との最後のお別れの時間を、穏やかにお過ごしください。
【関連記事】
- 葬式の花代の勘定科目は?経費計上の仕訳と注意点を解説
- 葬式でデカリボンはマナー違反?服装・髪飾りの許容範囲を解説
- 今日亡くなったら葬式はいつ?友引を避ける日程の決め方
- 大安に葬式はだめ?避けるべき?友引は?【迷いを解消】
- 葬式の帰り道、寄り道はしても大丈夫?マナーと注意点
【参考資料】