「友引に葬式を行うなんて、非常識だ」
もしかしたら、あなたも誰かからそう言われたり、そんな話を耳にしたりして、不安な気持ちでこのページを開いたのかもしれません。
大切な人との最後のお別れの儀式だからこそ、マナー違反や不快な思いは誰にもさせたくない、そう考えるのは当然のことです。
しかし、結論から言うと、友引の葬式は一概に「非常識」と断言できるものではありません。
この記事では、なぜそのように言われるのかという背景から、現代の葬儀事情、そしてやむを得ず友引に執り行う場合の具体的なマナーまで、あなたの心に寄り添いながら、一つひとつ丁寧に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、あなたの不安はきっと解消されているはずです。
友引に葬式は避けるべき?「非常識」と言われる理由
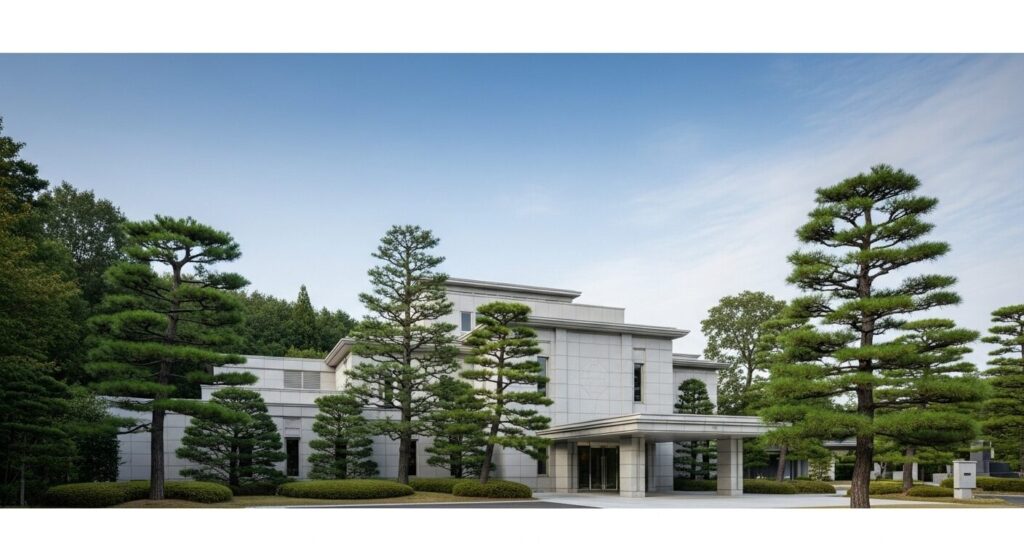
葬式の知恵袋・イメージ
そもそも、なぜ「友引に葬式をしてはいけない」という考えが、これほどまでに広まっているのでしょうか。
その背景には、古くからの暦と、そこから生まれた迷信が深く関わっています。
「友を引く」という迷信の由来と六曜の意味
カレンダーで「大安」や「仏滅」といった文字を見かけたことがあると思います。
あれは「六曜(ろくよう)」と呼ばれる、中国から伝わった暦注(暦に書かれる吉凶などの情報)の一種です。
| 六曜の種類 | 意味 |
| 先勝(せんしょう) | 午前は吉、午後は凶 |
| 友引(ともびき) | 朝晩は吉、昼は凶。勝負なしの日。 |
| 先負(せんぷ) | 午前は凶、午後は吉 |
| 仏滅(ぶつめつ) | 一日中、万事に凶 |
| 大安(たいあん) | 一日中、万事に大吉 |
| 赤口(しゃっこう) | 昼のみ吉、朝晩は凶 |
実は、「友引」はもともと「共引」と書き、「勝負事で共に引き分ける日」、つまり良くも悪くもない日とされていました。
それが、いつしか「友」という字が当てられ、「友を(冥土へ)引き寄せる」という意味に解釈されるようになり、葬儀のようなお悔やみ事を避けるべき日、という迷信が生まれたのです。

言葉のイメージって怖いですよね。本来の意味を知ると、少し冷静に考えられるようになります。
仏教の教えと六曜は本来関係がない
ここで非常に大切なことをお伝えします。
それは、仏教の教えと、先ほど説明した六曜は、全くの無関係であるということです。
六曜はあくまで民間の俗信(迷信)であり、お釈迦様の教えの中に「この日に葬儀をしてはいけない」といったものは一切ありません。
故人の冥福を祈り、心を込めて見送ることに、日の吉凶は関係ないというのが仏教本来の考え方なのです。
このことを知るだけでも、少し心が軽くなるのではないでしょうか。
地域の風習や慣習による影響も
とはいえ、理屈ではそうであっても、私たちの生活には地域の風習や長年の慣習が根強く残っています。
特にご年配の方々の中には、「友引の葬儀は避けるのが当たり前」と考えている方がいらっしゃるのも事実です。
「非常識」という言葉が出てくる背景には、この世代間の価値観の違いや、地域社会で大切にされてきた慣習が影響しているのです。
【結論】友引の葬式は絶対にダメではない!ただし注意が必要

葬式の知恵袋・イメージ
ここまでの話をまとめると、宗教的な理由で友引の葬儀が禁じられているわけではありません。
しかし、現実問題として、友引に葬儀(特に火葬)を行うのは難しいケースが多いのです。
その最大の理由を見ていきましょう。
全国の多くの火葬場が友引を休業日に設定している
これが、友引に葬儀ができない最も大きな「物理的」な理由です。
「友引に葬儀を避ける」という世間一般の慣習に合わせて、多くの自治体が運営する火葬場が、友引を職員の休日や施設のメンテナンス日に定めています。
つまり、葬儀(告別式)を行いたくても、その日に火葬ができないという状況が生まれるのです。
葬儀の日程は、まず火葬場の予約を確保してから決めるのが一般的な流れです。
そのため、結果的に友引を避けて葬儀の日程が組まれることがほとんど、というわけなのです。

実際に祖父の葬儀の際、葬儀社の方から真っ先に「火葬場の空き状況です」と説明を受けました。
宗派による考え方の違い【浄土真宗は問題なし】
先ほど仏教と六曜は無関係だと述べましたが、宗派によってはその姿勢をより明確に打ち出しているところもあります。
その代表が「浄土真宗」です。
浄土真宗では、「迷信に惑わされてはならない」という教えから、六曜を一切気にしません。
そのため、ご自身の家が浄土真宗であれば、親族などにも説明がしやすく、友引に葬儀を行うことへの抵抗は少ないかもしれません。
近年では、他の宗派でも六曜を気にしないお寺が増えてきています。
「お通夜」なら友引でも問題なく行える?
「葬儀はダメでも、お通夜ならいいの?」という疑問もよく聞かれます。
これについては、友引の日にお通夜を執り行うことは、一般的に問題ないとされています。
お通夜は故人と過ごす最後の夜であり、告別(お別れ)の儀式ではないため、「友を引く」という迷信には当たらない、と解釈されているからです。
そのため、以下のような日程はごく自然に組まれます。
- 1日目(友引): お通夜
- 2日目(先負など): 葬儀・告別式、火葬
この流れであれば、慣習にも配慮しつつ、スムーズに儀式を進めることができます。
友引に葬儀を執り行う場合の確認事項とマナー

葬式の知恵袋・イメージ
火葬場の営業など、様々な事情が重なり、どうしても友引に葬儀や告別式を行わざるを得ないケースもあるでしょう。
そんな時にトラブルを避け、故人を穏やかに見送るために、心に留めておきたいマナーと確認事項があります。
親族や参列者への事前の相談と丁寧な説明
最も大切なのが、周囲への配慮です。
特にご年配の親族には、「なぜ友引に執り行うのか」という理由を、あなたの言葉で丁寧に説明しましょう。
一方的に決定事項として伝えるのではなく、相談する姿勢が、相手の理解を得るための鍵となります。
【伝え方の例文】
「火葬場の予約がなかなか取れず、故人を長く安置しておくのも心苦しいため、皆様には大変恐縮ですが、友引の日に告別式を執り行わせていただけないでしょうか。」
このように、やむを得ない事情であることを誠心誠意伝えることで、多くの方は納得してくださるはずです。

「常識がない」と思われるのは、説明不足が原因のほとんど。丁寧なひと言が人間関係を守ります。
故人の遺志や家族の意向を最優先に
世間の常識や迷信も気になるところですが、何よりも優先すべきは「故人の遺志」と「遺された家族の想い」です。
故人が生前から「形式にはこだわらないでほしい」と望んでいたかもしれません。
家族が「一日でも早く安らかに見送ってあげたい」と願っているかもしれません。
「非常識」という外からの声に惑わされず、自分たちが納得できるお別れの形を一番に考えてください。
火葬日をずらす「前火葬」や「骨葬」という選択肢
もし、友引に火葬場が休業しているけれど、その日に告別式を行いたい場合、「骨葬(こつそう)」という方法があります。
これは、告別式の前に火葬を済ませ、お骨の状態で葬儀・告別式を行う形式です。
| 日程パターン | 1日目 | 2日目(友引) | 3日目 | メリット・デメリット |
| 一般的な流れ | 通夜 | 告別式・火葬(不可) | – | 火葬場が休業のため、この日程は組めない。 |
| 日程をずらす | 通夜 | (安置) | 告別式・火葬 | 安置期間が1日長くなる。 |
| 骨葬(前火葬) | 通夜・火葬 | 告別式(お骨で) | – | **友引でも告別式が可能。**火葬に立ち会える人が限られる場合がある。 |
この「骨葬」は、北海道や東北地方など、地域によっては一般的な葬儀形式でもあります。
どうしても日程の都合がつかない場合の有効な選択肢として、覚えておくとよいでしょう。
また、一部の地域では、「友を引かないように」という想いを込めて、「友引人形(友人形)」という身代わりの人形を棺に入れる風習もあります。
不安な気持ちが少しでも和らぐのであれば、こうした風習を取り入れるのも一つの方法です。
まとめ

葬式の知恵袋・イメージ
最後に、この記事の要点をもう一度振り返りましょう。
- 「友引の葬式が非常識」というのは、六曜の「友引」という言葉から生まれた迷信が根拠。
- 仏教の教えと六曜は全くの無関係であり、本来は気にする必要はない。
- ただし、多くの火葬場が友引を休業日にしているため、物理的に葬儀・火葬ができないことが多い。
- やむを得ず友引に執り行う場合は、親族への丁寧な説明が何よりも大切。
- 形式に惑わされず、故人を偲び、心を込めて見送る気持ちが最も重要。
「友引」というたった一つの言葉に、心をすり減らす必要はありません。
大切なのは、世間の常識に合わせること以上に、あなたとご家族が故人を想い、納得のいく形でお別れをすることです。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、心穏やかに大切な方を見送るための一助となれたなら、これほど嬉しいことはありません。
【関連記事】
- 葬式の生花の読み方は「せいか」?意味や供花との違い、マナーを解説
- 葬儀でもピアスが外せない時の対処法。基本マナーや隠し方も解説
- 通夜や葬式の日程、日にちがあくのはなぜ?理由と対応を解説
- 「良いお葬式」の言い換え表現集|遺族に気持ちが伝わる言葉
- 葬式休みの別の言い方は?「忌引」の読み方や意味を分かりやすく解説
【参考資料】

