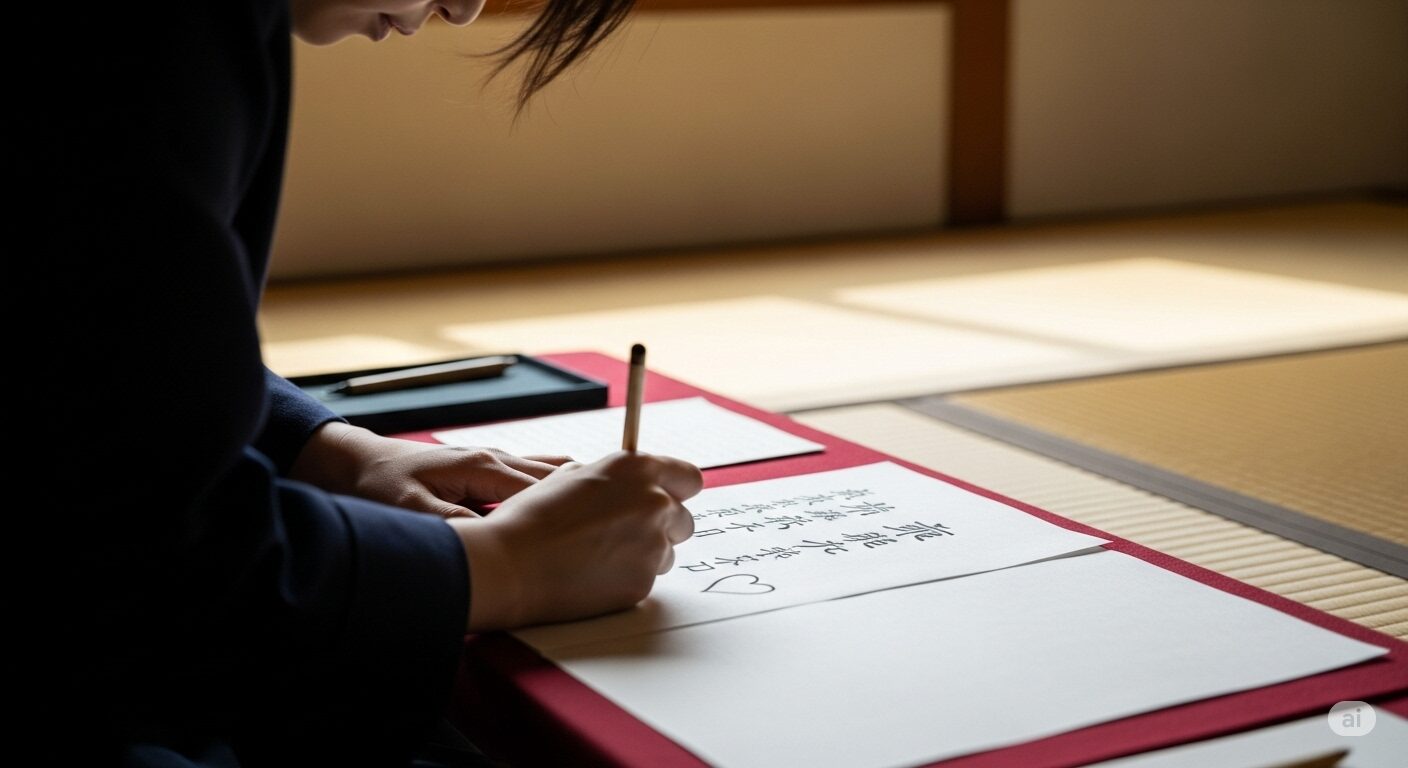大好きだったおじいちゃん、おばあちゃんとの突然のお別れ。
言葉にできないほどの悲しみの中で、「孫として何かできることはないだろうか」「感謝の気持ちを形にして伝えたい」そう考えていらっしゃるのではないでしょうか。
その一つの方法が、孫一同からの「寄せ書き」です。
しかし、葬儀という厳粛な場で、寄せ書きのようなものを贈っても良いのだろうか、マナー違反にならないだろうかと、不安に思うお気持ちも当然のことと思います。
この記事では、そんなあなたの不安を解消し、心からの感謝と愛情が伝わる最高の寄せ書きを贈るためのお手伝いをします。
書き方の具体的な例文から、失礼にならないためのマナー、色紙の選び方まで、一つひとつ丁寧に解説していきますので、どうぞ最後までお付き合いください。
葬儀で孫から寄せ書きを贈るのは失礼?基本的なマナーを解説
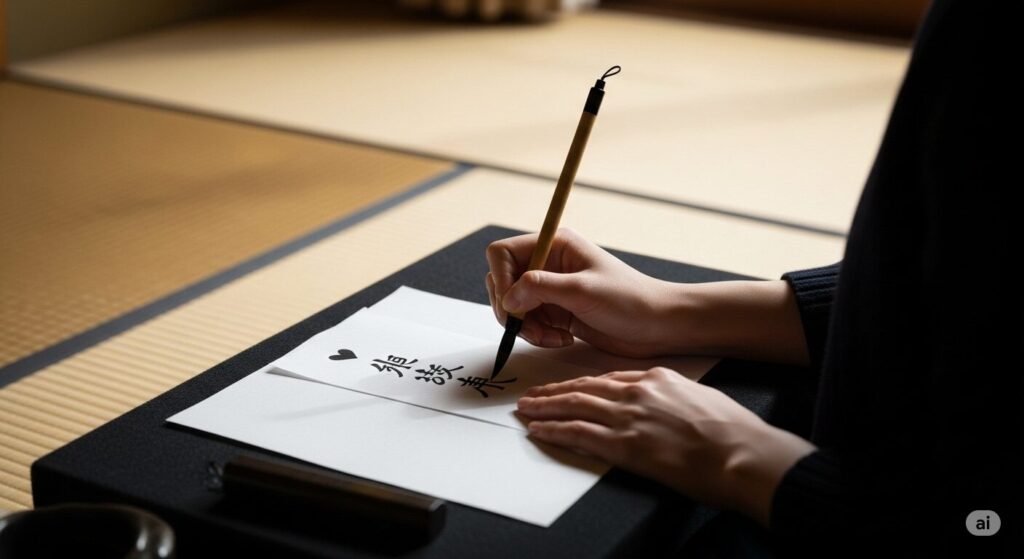
葬式の知恵袋・イメージ
まず最初に、一番の疑問にお答えします。
結論から言うと、葬儀に孫から寄せ書きを贈ることは、決して失礼にはあたりません。
むしろ、故人を想う孫たちの温かい気持ちが伝わる、とても素敵な贈り物になります。
故人への感謝を伝える贈り物として喜ばれる
寄せ書きは、孫たちから故人へ贈る「最後の手紙」のようなものです。
生前は照れくさくてなかなか言えなかった「ありがとう」の言葉や、楽しかった思い出を綴ることで、故人に心からの感謝を伝えられます。
そして、それは残されたご遺族、つまりあなたのご両親や叔父叔母にとっても、大きな慰めとなります。
「あの子たちに、こんなに想われていたんだな」と、孫たちの愛情のこもったメッセージを読むことで、ご遺族の悲しみが少しでも和らぐきっかけになるのです。

祖父の葬儀で寄せ書きを渡した際、父が涙ぐみながら「ありがとうな」と言ってくれたのを覚えています。故人だけでなく遺族の心にも届くものだと実感しました。
寄せ書きを渡すタイミングはいつ?誰に渡すべき?
寄せ書きが完成したら、いつ、誰に渡せば良いのでしょうか。
決まったルールはありませんが、以下のタイミングが一般的です。
- お通夜の始まる前
- 告別式の始まる前
- 出棺前、最後のお別れの時
一番確実なのは、事前に喪主(またはご自身の親)に「孫一同から寄せ書きを準備したのだけど、いつ渡せば良いかな?」と相談しておくことです。
葬儀当日はご遺族も慌ただしくしているため、事前に一声かけておくとスムーズに受け取ってもらえます。
渡す相手は、葬儀の責任者である喪主にお渡しするのが最も丁寧です。
棺に入れる際に気を付けたいこと
寄せ書きを「棺に入れて一緒に送り出してあげたい」と考える方も多いでしょう。
その場合、一つだけ注意点があります。
それは、棺に入れられるものは「燃えやすいもの」に限られるということです。
一般的な紙や布製の色紙であれば、ほとんどの場合問題ありません。
しかし、以下のような装飾が付いているものは避けましょう。
- プラスチック製の飾り
- 金属製のクリップやフレーム
- ガラスやアクリル製のパーツ
これらは燃え残ってしまう可能性があるため、棺に入れることができません。
最終的な判断は火葬場の規則や葬儀社の方針によりますので、棺に入れたい場合は、必ず事前に葬儀社のスタッフに「この寄せ書きは棺に入れても大丈夫でしょうか?」と確認するのが最も安心です。
【状況別】感謝が伝わる葬式の寄せ書きメッセージ例文集

葬式の知恵袋・イメージ
「いざ書こうと思っても、どんな言葉を書けばいいか分からない…」
そんな方のために、状況別のメッセージ例文をいくつかご紹介します。
大切なのは、上手な文章を書くことではありません。あなたの心からの言葉で、感謝や思い出を伝えることです。以下の例文を参考に、あなたらしいメッセージを考えてみてください。
「孫一同」として贈る場合のメッセージ例文
- シンプルな例文
おじいちゃんへ
たくさんの愛情をありがとう。
いつも優しかったおじいちゃんのことが大好きです。
どうか安らかにお眠りください。
孫一同
- 思い出を交えた例文
大好きなおばあちゃんへ
おばあちゃんが作ってくれた卵焼きの味、夏休みにみんなで遊んだこと、全部が大切な宝物です。
いつも笑顔で迎えてくれて本当にありがとう。
これからは、おばあちゃんが見守ってくれる空に向かって、みんなで頑張ります。
孫一同
個人の立場で書く場合のメッセージ例文
- 感謝を伝える例文
おじいちゃんへ
小さい頃、キャッチボールをしてくれたこと、忘れません。おじいちゃんが教えてくれた優しさを、これからも大切にしていきます。本当にありがとうございました。
- 約束を伝える例文
おばあちゃんへ
「いつでも前向きにね」というおばあちゃんの言葉を胸に、私も強く生きていきます。心配しないで、ゆっくり休んでね。今まで本当にありがとう。
小さい子供やひ孫が書く・描く場合のポイント
まだ文字が書けない小さなお子さんや、ひ孫さんからのメッセージは、場を和ませる温かい光になります。
無理に文字を書かせる必要はありません。
- 似顔絵を描く
- お花やハートの絵を描く
- 手形や足形を押す
これだけでも、故人を想う純粋な気持ちは十分に伝わります。
もし親が代筆する場合は、「〇〇(ひ孫の名前)より『おじいちゃん、だーいすき』」のように、子供の言葉をそのまま書いてあげると、より気持ちが伝わりやすくなりますよ。

当時4歳だった姪が描いた祖母の似顔絵は、決して上手ではなかったですが、それを見た親族みんなの顔がほころびました。子供の存在は本当に偉大です。
書くときに避けたい忌み言葉や表現の注意点
お悔やみの場では、不幸が重なることや死を直接的に連想させる「忌み言葉」を避けるのがマナーです。
寄せ書きでも同様に配慮しましょう。
| 種類 | 避けるべき言葉の例 | 言い換えの例 |
| 重ね言葉 | いろいろ、ますます、たびたび、くれぐれも | 多くの、さらに、よく、どうぞ |
| 不幸が続くことを連想させる言葉 | 続く、再び、追って | – |
| 不吉な言葉 | 消える、浮かばれない、迷う | – |
| 直接的な表現 | 死亡、急死、生きていた頃 | ご逝去、突然のこと、ご生前 |
| 宗教・宗派によっては不適切 | 成仏、冥福、天国 | 安らかな眠り、神様のもとへ |
「死」や「苦」を連想させる「四」や「九」といった数字も避けた方が無難です。
葬儀にふさわしい寄せ書きの準備と書き方
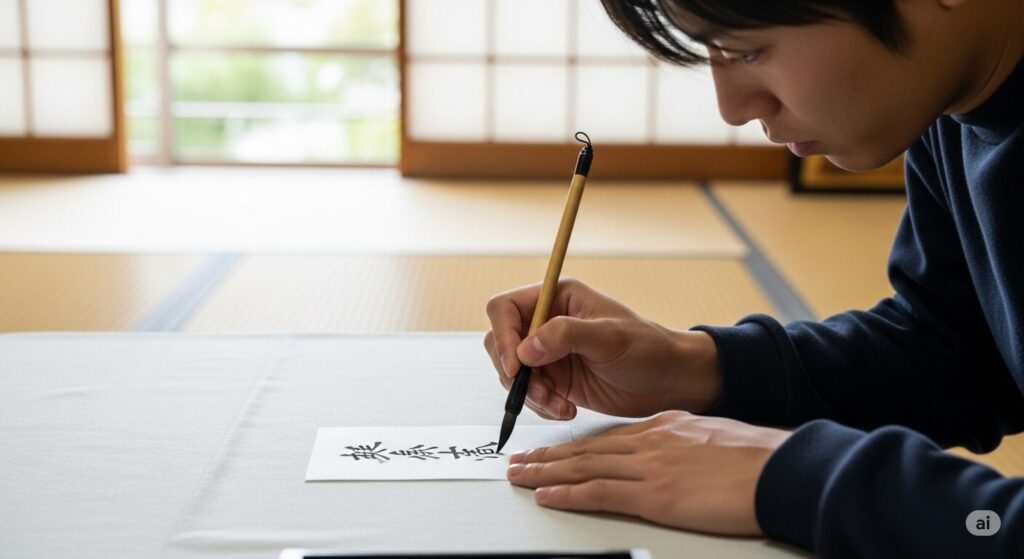
葬式の知恵袋・イメージ
メッセージの内容が決まったら、次は物理的な準備です。
どんな色紙やペンを選べば良いか解説します。
色紙の選び方|落ち着いたデザインを選ぼう
文房具店やオンラインストアには様々な色紙がありますが、葬儀の場にふさわしいものを選びましょう。
- 色: 白無地が最も無難です。その他、薄い水色、クリーム色、淡い緑色など、控えめで落ち着いた色合いのものを選びましょう。
- デザイン: 無地が基本ですが、故人がお好きだった桜や藤の花、風景などが薄く描かれている程度であれば問題ありません。金銀の派手な装飾や、原色を使ったカラフルなデザインは避けましょう。
使用するペンの色|薄墨と黒の使い分け
香典の表書きなどで使われる「薄墨」。これは「悲しみの涙で墨が薄まってしまった」「急なことで墨をする時間もなかった」という意味合いを表すためのものです。
では、寄せ書きも薄墨で書くべきなのでしょうか?
これには様々な考え方がありますが、寄せ書きの場合は、必ずしも薄墨にこだわる必要はありません。
寄せ書きは不祝儀袋とは異なり、故人への感謝を伝える手紙としての側面が強いため、読みやすい濃い黒のペンで書いても全く失礼にはあたりません。
むしろ、たくさんの孫が書く寄せ書きでは、読みやすさが大切です。
サインペンやボールペンなど、滲みにくく書きやすい黒いペンを選ぶのがおすすめです。
イラストや写真を添える際の配慮
文字だけでなく、何かを添えたいと考えることもあるでしょう。
- イラスト: 故人が好きだった花や趣味の道具(釣り竿や編み物など)を、メッセージの横に小さく添える程度であれば、心が和む素敵なアクセントになります。
- 写真: 故人との思い出の写真を貼るのも、ご遺族に喜ばれることが多いです。みんなで笑っている写真などは、故人の人柄を偲ぶきっかけにもなります。ただし、棺に入れる場合は写真も燃えてしまうため、データで共有したり、別にプリントしてご遺族に渡したりする配慮ができると、より丁寧です。
葬式の寄せ書きに関するよくある質問

葬式の知恵袋・イメージ
最後に、寄せ書きに関して多くの方が抱く疑問にお答えします。
Q. 寄せ書きの代わりに手紙を書いてもいい?
A. はい、もちろん問題ありません。
寄せ書きのようにみんなで共有する形ではなく、一対一で個人的な想いをじっくりと伝えたい場合は、手紙の方が適していることもあります。
白い無地の便箋や、薄い色のシンプルな便箋に、心を込めて綴りましょう。書いた手紙は、封筒に入れて喪主にお渡しするか、許可を得て棺に入れます。
Q. 遠方に住む孫がいる場合どうやってまとめる?
A. 便利なツールや郵送を活用しましょう。
孫がそれぞれ離れた場所に住んでいる場合、一つの色紙に集まって書くのは難しいですよね。その場合は、以下のような方法があります。
- 方法1:データで集約する(おすすめ)
- 代表者が色紙の本体を準備します。
- 各孫は、白い紙にメッセージを書き、それをスマートフォンで撮影して代表者に送ります。
- 代表者は、送られてきたメッセージの画像を印刷し、色紙にきれいに貼り付けます。
この方法が最もスピーディーで確実です。
- 方法2:オンライン寄せ書きサービスを利用する
ウェブ上でメッセージを集められるサービスを利用し、完成したものを印刷して色紙に貼る、またはそのまま印刷して渡す方法もあります。
- 方法3:郵送でリレーする
時間に余裕があれば、色紙を次の人へ郵送で回していく方法もあります。ただし、葬儀までの時間が限られているため、あまり現実的ではないかもしれません。

海外に住む従兄弟とは、メッセージをデータで送ってもらい、私が印刷して貼りました。離れていても気持ちは一つ。便利な時代になったなと感じましたね。
Q. 宗教や宗派によって違いはある?
A. 配慮が必要な場合があります。
日本の葬儀の多くは仏式ですが、他の宗教・宗派の場合は注意が必要です。
- キリスト教: 「冥福」「成仏」「供養」といった仏教用語は使いません。「安らかな眠りをお祈りいたします」「神の御許で安らかに」といった表現を用います。
- 神道: こちらも仏教用語は使いません。「御霊(みたま)のご平安をお祈りいたします」といった表現が適切です。
ただ、孫から祖父母への個人的なメッセージであれば、厳密な作法よりも故人を想う気持ちが優先されることがほとんどです。
それでももし不安な場合は、ご両親や葬儀社のスタッフに「寄せ書きを考えているのですが、宗教的に問題ないでしょうか?」と確認するのが最も確実です。
まとめ

葬式の知恵袋・イメージ
この記事では、おじいちゃん、おばあちゃんの葬儀に際して、孫から贈る寄せ書きのマナーや書き方について詳しく解説してきました。
- 孫からの寄せ書きは失礼にはならず、むしろ喜ばれる贈り物
- 渡すタイミングや棺に入れるかは、事前に喪主や葬儀社に相談するのが安心
- メッセージは上手な文章より、心からの感謝や思い出を自分の言葉で綴ることが一番大切
- 色紙やペンは、落ち着いたデザインや色のものを選ぶ
- 遠方の孫とは、データなどを活用して協力する
寄せ書きを準備する時間は、故人との楽しかった思い出を孫同士で語り合う、かけがえのない時間にもなります。
悲しみは尽きないと思いますが、たくさんの「ありがとう」を込めた寄せ書きで、大好きだったおじいちゃん、おばあちゃんを温かく送り出してあげてください。
あなたの優しい気持ちが、きっと故人とご遺族の心に届くはずです。
【関連記事】
- 【男性向け】葬式の袱紗はどこに入れる?スーツでの正しい持ち方
- 友引に葬式は非常識?知っておきたい理由と現代の事情
- 葬式の生花の読み方は「せいか」?意味や供花との違い、マナーを解説
- 葬儀でもピアスが外せない時の対処法。基本マナーや隠し方も解説
- 通夜や葬式の日程、日にちがあくのはなぜ?理由と対応を解説
【参考資料】