大切な方との突然のお別れは、深い悲しみと共に、やらなければならないことの多さに戸惑われることと思います。
特に、通夜や葬儀の日程を決めるにあたり、「暦(こよみ)の上で良い日、悪い日があるのだろうか」「友引に葬儀をしてはいけないと聞いたけど本当?」といった疑問や不安を感じる方は少なくありません。
この記事では、そんなあなたの不安に寄り添い、通夜・葬式と暦の関係、そして後悔のないお見送りのための日程の決め方について、一つひとつ丁寧に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、暦に関する迷いが消え、自信を持って大切な方のお見送りの準備を進められるようになっているはずです。
通夜や葬式と暦(六曜)の基本的な関係性
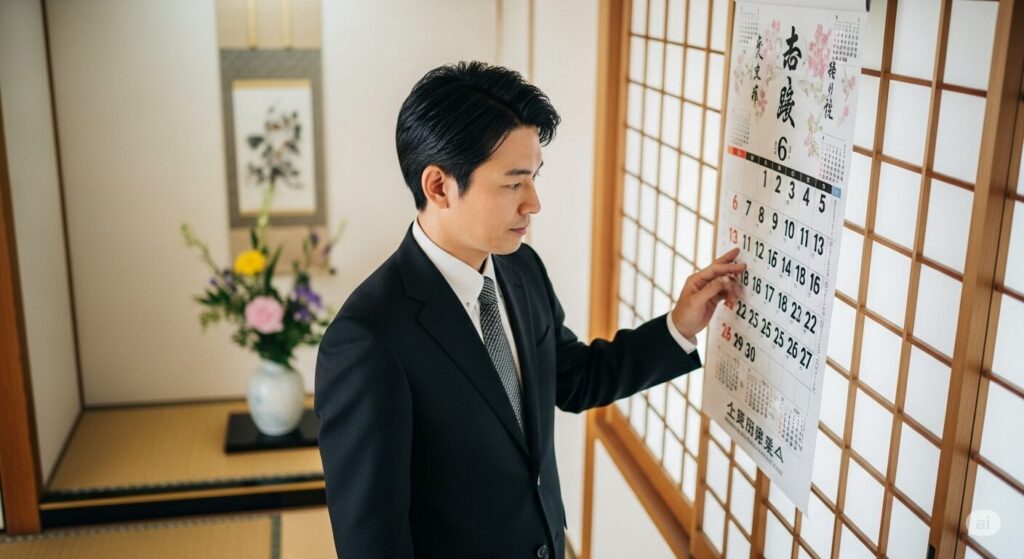
葬式の知恵袋・イメージ
まず、多くの方が気にされる暦、特に「六曜(ろくよう)」と葬儀の関係について、核心からお伝えします。
仏教と六曜は本来無関係!ただし風習への配慮は必要
驚かれるかもしれませんが、仏教の教えの中に、六曜に関する記述は一切ありません。
六曜(大安、友引、先勝、先負、赤口、仏滅)は、もともと中国で生まれ、時刻の吉凶を占うために使われていた考え方です。
つまり、仏事である通夜や葬儀と、六曜の吉凶は本来まったくの無関係なのです。
ですから、宗教的な観点から言えば「どの日に葬儀を行っても問題ない」というのが答えになります。
しかし、日本では「友引に葬儀を避ける」という風習が、特に年配の方を中心に根強く残っているのも事実です。
大切なのは、故人を思う気持ちと、集まる方々が心穏やかにお見送りできること。
そのため、ご自身の考えだけで進めるのではなく、ご親族の意向にも耳を傾け、配慮する姿勢が求められます。

僕の祖母の葬儀でも、親族の強い意向で友引は避けました。形式よりも皆が納得してお見送りすることが一番大切だと感じましたね。
なぜ?「友引」に葬式を避ける理由とその由来
では、なぜ「友引」に葬儀を避ける風習が広まったのでしょうか。
これには、言葉の語呂合わせが大きく影響しています。
もともと友引は「共引」と書き、「勝負事で何事も引き分けになる日」という意味でした。
これがいつしか「友を引く」という字に変わり、「故人が友を冥土へ引いていってしまう」と解釈されるようになったのです。
あくまで迷信や語呂合わせから来た考え方ですが、大切な方を亡くしたばかりの遺族の心情として、「縁起の悪いことは避けたい」と思うのは自然なことかもしれません。
この風習が社会に定着した結果、後述するように多くの火葬場が友引を休業日としています。
「友引」の通夜は行っても良い?葬式との違いを解説

葬式の知恵袋・イメージ
「友引の葬儀は避けるべきなのは分かったけど、お通夜はどうなの?」という疑問もよく聞かれます。
結論から言うと、友引にお通夜を執り行うことは、一般的に問題ないとされています。
お通夜と告別式(葬式)で日程の考え方は違う
その理由を理解するために、お通夜と告別式(葬式)の目的の違いを知っておきましょう。
- お通夜:もともとは、親しい身内が夜通し故人に寄り添い、邪霊などから守るための儀式。故人との最後の夜を過ごす、内輪の儀式という意味合いが強いです。
- 告別式(葬式):故人と縁のあった方々が最後の別れを告げ、社会的に故人の死を悼む儀式です。火葬場へ向かう「出棺」もこの儀式に含まれます。
通夜は「お別れの儀式」ではないため友引でも可能
「友を引く」と連想されるのは、故人を火葬に付し、この世とのお別れをする「出棺」や「火葬」です。
お通夜は、まだ故人と最後の夜を過ごしている段階であり、お別れの儀式ではありません。
そのため、「友を引く」ことには繋がらないと考えられ、友引にお通夜を行っても差し支えないとされているのです。
むしろ、友引にお通夜を行い、翌日の六曜が良い日に告別式・火葬を行うという日程は、非常に多く見られます。

友引に通夜ができると、日程調整の幅がぐっと広がります。火葬場の予約もスムーズに進むことが多いので、覚えておくと安心ですよ。
【六曜一覧】通夜・葬式との関係性とそれぞれの意味

葬式の知恵袋・イメージ
友引以外の六曜は、葬儀とどのように関係するのでしょうか。
基本的にはどの六曜でも問題ありませんが、それぞれの意味を知っておくと、親族への説明もしやすくなります。
| 六曜の種類 | 読み方 | 意味 | 葬儀との関係 |
| 友引 | ともびき | 引き分けになる日。朝晩は吉、昼は凶。 | 葬儀・火葬は避ける傾向。通夜は問題なし。 |
| 大安 | たいあん | 万事において大吉の日。 | 気にせず行ってよい。慶事のイメージが強いが問題なし。 |
| 仏滅 | ぶつめつ | 万事に凶である日。 | 「仏が滅する」という字面から葬儀に適するとも言われるが、本来は無関係。 |
| 先勝 | せんしょう | 午前は吉、午後は凶。 | 気にせず行ってよい。行うなら午前中が良いとする考え方もある。 |
| 先負 | せんぶ | 午前は凶、午後は吉。 | 気にせず行ってよい。行うなら午後が良いとする考え方もある。 |
| 赤口 | しゃっこう | 祝い事は大凶。正午頃のみ吉。 | 気にせず行ってよい。火や刃物に注意する日とされる。 |
このように、友引以外は特に葬儀と結びつけて考えられることはありません。
「仏滅」は字のイメージから葬儀に適していると考える方もいますが、これも本来の仏教や六曜の意味とは異なります。
どんな日であっても、故人を偲ぶ気持ちがあれば、それが一番良い日と言えるでしょう。
暦よりも優先すべき!通夜・葬式の日程の決め方と流れ

葬式の知恵袋・イメージ
ここまで暦との関係を解説してきましたが、実は、実際の葬儀の日程を決める上では、暦(六曜)よりもはるかに優先すべき重要なことが3つあります。
慌ただしい中で判断を迫られますが、この優先順位を頭に入れておくと、スムーズに事を進めることができます。
最優先は火葬場の空き状況の確認
何よりもまず、火葬場の予約を確保することが最優先事項です。
法律上、亡くなってから24時間は火葬することができないと定められています。
そして、火葬場の予約が取れない限り、通夜や告別式の日程を確定させることができません。
特に都市部では火葬場が混み合っており、希望の日時に予約が取れないことも珍しくありません。
また、前述の通り友引を休業日としている火葬場が多いため、友引の翌日は予約が殺到しやすくなります。
まずは葬儀社と相談し、火葬場の空き状況を確認することから始めましょう。
宗教者(僧侶など)の都合を調整
菩提寺(ぼだいじ)がある場合や、お付き合いのある宗教者(僧侶など)に依頼する場合は、その方の都合を確認することも非常に重要です。
特に、お盆の時期やお彼岸の時期は、宗教者の方も多忙を極めます。
火葬場の予約と並行して、なるべく早く連絡を取り、都合の良い日時を伺いましょう。

葬儀社を決めると、担当者が火葬場と宗教者のスケジュール調整を代行してくれます。一人で抱え込まず、プロに頼るのが一番です。
親族や主な参列者が集まれる日程か
火葬場と宗教者の都合がついたら、次に親族や特に参列してほしい方々のスケジュールを確認します。
遠方に住んでいる親族がいる場合は、移動時間も考慮しなければなりません。
すべての方の都合を合わせるのは難しいかもしれませんが、故人と特に縁の深かった方々が参列できるよう、最大限の配慮をしたいものです。
亡くなった日から何日後までに行う?一般的な日数
法律では「死後24時間経過後」という決まりしかありませんが、一般的には、亡くなった日の翌日にお通夜、翌々日に告別式・火葬という流れが多く見られます。
しかし、これはあくまで最短の場合です。
火葬場の混雑状況や、遠方の親族が集まる時間などを考慮し、亡くなってから3〜5日後に葬儀を行うことも決して珍しくはありません。
日程が少し空いてしまっても、焦る必要はありません。
その分、故人との最後の時間をゆっくりと過ごし、お別れの準備を丁寧に進めることができると、前向きに捉えましょう。
通夜や葬式の日程に関するよくある質問

葬式の知恵袋・イメージ
最後に、日程に関して多くの方が抱く細かい疑問について、Q&A形式でお答えします。
Q1. 葬儀の日程は誰がどのように決めるのですか?
A1. 一般的には、喪主が中心となり、葬儀社の担当者や主な親族と相談しながら決定します。
まずは葬儀社に連絡し、プロのアドバイスを受けながら、先ほど解説した「火葬場」「宗教者」「親族」の3つのポイントを軸に調整していくのがスムーズです。
Q2. 六曜以外に葬儀を避けるべき日はありますか?
A2. 正月の三が日などは避けるのが一般的です。
これは、多くの火葬場や斎場が休業しているためです。
また、地域によっては特別な祭礼の日などを避ける風習がある場合もありますが、基本的には三が日以外で物理的に不可能な日はほとんどありません。
Q3. 友引に火葬場が休みの地域が多いのは本当ですか?
A3. はい、本当です。
「友引に葬儀をしない」という風習が根付いているため、需要が少ないことから、多くの自治体や民営の火葬場が友引を休業日として定めています。
ただし、すべての火葬場が休みというわけではなく、地域によっては友引でも稼働しているところもあります。
急ぐ事情がある場合は、葬儀社に友引でも利用できる火葬場がないか相談してみましょう。
まとめ

葬式の知恵袋・イメージ
今回は、通夜・葬儀の日程と暦(六曜)の関係について詳しく解説しました。
最後に、この記事の最も大切なポイントを振り返ります。
- 仏教と六曜は本来無関係。 葬儀の日柄を気にするのは、あくまで日本の風習。
- 「友引」の葬儀は避ける傾向があるが、それは「友を引く」という語呂合わせから。
- 友引にお通夜を行うことは問題ないとされるのが一般的。
- 日程決めは、①火葬場の空き ②宗教者の都合 ③親族のスケジュール を暦より優先する。
大切なのは、世間体や迷信に振り回されることではなく、故人を偲ぶ気持ちです。
そして、ご遺族や親しい方々が心から納得し、穏やかな気持ちで故人様をお見送りできること。
それが、何より素晴らしい供養になるはずです。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、後悔のないお別れの一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
【関連記事】
- お葬式でかける言葉の例文集|基本マナーとNGワードも解説
- 葬式の香典にピン札は失礼?知っておくべき包み方のマナー
- 葬式の行き帰りの服装マナーは?会場までの移動や着替えの疑問を解決
- 葬式の寄せ書き|孫からのメッセージ例文と失礼にならないマナー
- 【男性向け】葬式の袱紗はどこに入れる?スーツでの正しい持ち方
【参考資料】

