突然の訃報に際し、お通夜や葬儀に参列する準備を進める中で、「香典に包むお札は、新札(ピン札)でも良いのだろうか?」と、ふと手が止まってしまった経験はありませんか。
結婚式のご祝儀では新札を用意するのがマナーとされているため、弔事であるお葬式ではどうすれば良いのか、迷ってしまいますよね。
結論からお伝えしますと、お葬式の香典にピン札を包むのは、基本的には避けるのが無難とされています。
この記事では、長年にわたり様々な場面で冠婚葬祭のマナーに触れてきた私が、なぜピン札が避けられるのかという理由から、手元にピン札しかない場合の具体的な対処法、そして香典に関する様々な疑問まで、心を込めて丁寧にご説明します。
大切なのは、故人を悼み、ご遺族に寄り添うそのお気持ちです。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、心穏やかに故人をお見送りするための一助となれば幸いです。
葬儀でピン札(新札)がマナー違反とされる理由

葬式の知恵袋・イメージ
まず、なぜお葬式の香典でピン札がふさわしくないとされているのでしょうか。
これには、日本人の死生観や相手を思いやる文化に根差した、大きく二つの理由があると言われています。
「不幸を予期していた」という印象を与えてしまうため
これが、最も広く知られている理由です。
折り目のない綺麗な新札は、前もって銀行などで準備しないとなかなか手に入らないものです。
そのため、香典にピン札を入れると、「不幸が訪れることを予期して、あらかじめ準備していた」という印象をご遺族に与えかねないとされています。
訃報は突然訪れるものですから、「急いで駆けつけました」という気持ちを示す意味でも、あえて新札を避けるのが礼儀とされているのです。
新しいお札が「新たな不幸」を連想させるから
もう一つの理由として、縁起を担ぐという側面もあります。
「新しい」という言葉から、「新たな不幸が重なる、続く」といった不吉な連想を招くとして、気にされる方もいらっしゃいます。
これらの理由は、あくまでも受け取る側への配慮から生まれた慣習です。
絶対にダメという厳しい決まりではありませんが、ご遺族がどのように感じるかを第一に考え、避けるのが賢明と言えるでしょう。
【緊急】香典に使えるお札がピン札しかない時の対処法
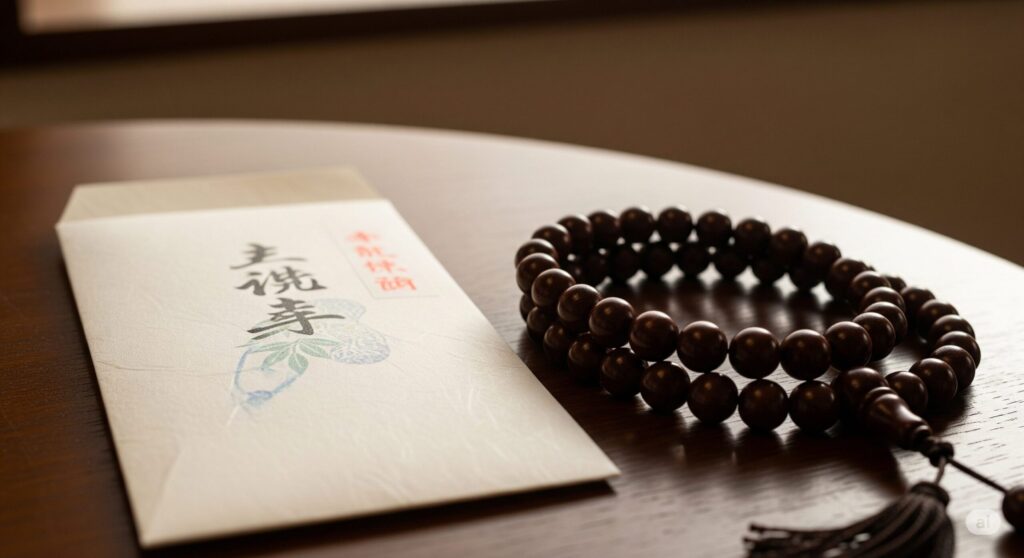
葬式の知恵袋・イメージ
理由がわかっても、いざという時に手元にピン札しかない、という状況は十分に考えられますよね。
私も以前、急な知らせで財布の中身を確認したら、たまたま下ろしたてのピン札しかなくて焦った経験があります。
そんな緊急時でも、失礼にあたらないようにできる簡単な対処法がありますので、ご安心ください。

ATMで下ろしたばかりでピン札しかなかった時は焦りました。でも、このひと手間を知っているだけで、落ち着いて対応できましたよ。
最も簡単!ピン札に一度折り目を付けてから包む方法
手元にピン札しかない場合、そのお札に自分で折り目を付けるのが、最も簡単で確実な対処法です。
わざわざ古いお札を探し回る必要はありません。
【折り目の付け方】
- ピン札を一枚、綺麗な机の上に置きます。
- 真ん中で、そっと二つ折りにします。
- しっかりと折り目を付けたら、もう一度開きます。
たったこれだけで、ピン札は「あらかじめ用意したものではない」という意味合いを持つお札に変わります。
ポイントは、わざとらしくクシャクシャにしないことです。
あくまでも自然な折り目を一つか二つ、丁寧につけるだけで十分です。
新札を旧札(古札)に交換できる場所はどこ?
もし時間に少しでも余裕があるのなら、銀行や郵便局の窓口で旧札への両替をお願いすることも可能です。
ただし、窓口は平日の日中しか開いていないため、夜間や土日の訃報の場合は難しいかもしれません。
また、両替機では新札が出てくることが多いため、窓口で直接お願いするのが確実です。
コンビニのATMを利用する際の注意点
「コンビニのATMで一度お金を預けて、もう一度引き出せば古いお札になるのでは?」と考える方もいるかもしれません。
これは一つの方法として試す価値はありますが、注意点もあります。
- 必ず旧札になるとは限らない: ATM内の現金が新しいものに補充された直後だと、再び新札が出てくる可能性があります。
- 手数料がかかる場合がある: 時間帯やご利用の金融機関によっては、預け入れや引き出しに手数料が発生します。
この方法は確実ではないため、やはり自分で折り目を付ける方法が最も現実的でおすすめです。
葬式の香典に適したお札の選び方と準備
では、どのようなお札を「適したお札」として準備するのが理想なのでしょうか。
少し使用感のある「旧札(古札)」が最も望ましい
香典で最も望ましいとされるのは、適度な使用感のある「旧札(古札)」です。
ここで言う「旧札」とは、破れていたり、シミだらけだったりする古いお札のことではありません。
現在、社会でごく普通に流通している、少しシワや折り目があるお札のことを指します。
これらのお札であれば、「急な訃報を聞いて、手持ちのお金で駆けつけました」という気持ちが伝わりやすくなります。
手元に綺麗なお札しかない場合はどう準備する?
もし手持ちのお札がどれも新札に近い綺麗なものばかりだった場合は、前述したように、そっと折り目を付けてから使いましょう。
「使い古した感じ」を出すために、わざとクシャクシャにする必要は全くありません。
故人やご遺族への敬意を込めて、あくまでも丁寧に取り扱うことが大切です。

このマナーを知ってから、財布に数枚、少し使い込んだお札を意識して残しておくようになりました。いざという時の安心感が違います。
シワや汚れがひどいお札は避けるのが無難
いくら旧札が良いと言っても、あまりにも汚れていたり、破れていたり、セロハンテープで補修されていたりするお札を包むのは失礼にあたります。
これは故人への敬意を欠く行為と見なされてしまいますので、最低限の礼儀として、綺麗で状態の良い旧札を選びましょう。
大丈夫?お札の入れ方や向きなど香典の基本マナー
お札の種類だけでなく、香典袋へのお金の入れ方にもマナーがあります。
細かな点ですが、知っておくことで、より丁寧に弔意を示すことができます。
お札の向きは?肖像画を裏向き・下向きに入れるのが基本
香典袋の中袋にお札を入れる際は、お札の肖像画(顔)が描かれている面を裏側(中袋の裏面)に向け、さらに肖像画が下になるようにして入れます。
これには、「悲しみに顔を伏せる」「お悔やみの場では顔を上げられない」といった、深い悲しみを表現する意味が込められています。
【お札の入れ方まとめ】
- 中袋の表面から見て、お札は裏側を向いている状態にする。
- お札の肖像画が、袋の底側に来るように入れる。
複数枚入れる場合はお札の向きを揃える
お札を複数枚入れる場合は、すべての向きをきちんと揃えましょう。
バラバラの向きで入れるのは、雑な印象を与えてしまうため避けるべきです。
中袋へのお金の入れ方と金額の書き方
多くの場合、香典袋にはお金を直接入れるための「中袋(中包み)」が付いています。
お札は必ずこの中袋に入れてから、外袋に収めましょう。
中袋の表面には包んだ金額を、裏面には自分の住所と氏名を書きます。
金額を書く際は、改ざんを防ぐためにも旧字体の漢数字である「大字(だいじ)」を用いるのが最も丁寧な書き方です。
| 金額(算用数字) | 金額(大字) |
| 3,000円 | 金参阡圓 |
| 5,000円 | 金伍阡圓 |
| 10,000円 | 金壱萬圓 |
| 30,000円 | 金参萬圓 |
ただし、近年では「金三千円」「金五千円」のように、一般的な漢数字で書くことも許容されています。
これってOK?葬式のお金に関するよくある質問
最後に、多くの方が疑問に思うであろう、お金に関する細かい質問にお答えします。
結婚式でもらった綺麗なご祝儀袋のお札は使える?
結婚式のご祝儀でいただいたピン札を手元に置いている方もいらっしゃるかもしれません。
これを使うこと自体に問題はありませんが、やはりピン札であることには変わりありません。
香典として使う場合は、必ず一度折り目を付けてから包むようにしましょう。
お布施や御車代もピン札は避けるべき?
これは非常に重要なポイントです。
香典とは異なり、お坊さん(僧侶)にお渡しする「お布施」や「御車代」「御膳料」などは、むしろ新札を用意するのが丁寧なマナーとされています。
なぜなら、これらは不幸に対するお悔やみの気持ちではなく、読経や戒名に対する「感謝の気持ち」や「対価」としてお渡しするものだからです。
感謝を示すために、あらかじめ準備した綺麗な新札を包むのが礼儀となります。
この違いは、ぜひ覚えておいてください。

香典とお布施でマナーが逆になるのは驚きですよね。相手への「気持ちの種類」を考えれば、自然と理解できるかもしれません。
地域や宗教によって考え方に違いはある?
この記事でご紹介したのは、あくまでも日本全国で広く一般的とされているマナーです。
地域や家の慣習、また宗教によっては、ピン札を全く気にしないという場合もあります。
もし判断に迷うようなことがあれば、ご両親や年長の親族、あるいは葬儀社のスタッフの方にそっと確認してみるのが最も確実で安心です。
まとめ
今回は、お葬式の香典でピン札が避けられる理由と、その対処法について詳しく解説しました。
最後に、この記事の要点をまとめておきます。
- 香典にピン札は避けるのが無難: 「不幸を予期していた」と思わせないための配慮。
- ピン札しかない場合: 自分でそっと中央に折り目を一つ付ければOK。
- 最適なお札: 少し使用感のある「旧札(古札)」が望ましい。ただし、汚すぎるお札はNG。
- お札の入れ方: 肖像画を裏向き・下向きにして入れる。
- 注意点: 僧侶へのお布施は、感謝の気持ちなので逆に新札を用意するのがマナー。
様々なマナーやしきたりがありますが、その根底にあるのは、いつの時代も変わらない「故人を悼み、ご遺族を思いやる心」です。
形式にとらわれすぎる必要はありませんが、こうした知識を持っておくことで、より深く、そして穏やかな気持ちで故人様とのお別れの時間を過ごせるはずです。
あなたのその温かいお気持ちが、ご遺族にとって何よりの慰めとなることでしょう。
【関連記事】
- 葬式の盛花とは?相場・マナーから札名の書き方まで解説
- 葬式でご飯に箸を立てる意味とは?枕飯の作法や由来を解説
- 通夜・葬式と暦の関係は?友引に避けるべきか日程の決め方を解説
- お葬式でかける言葉の例文集|基本マナーとNGワードも解説
- 葬式の香典にピン札は失礼?知っておくべき包み方のマナー
【参考資料】

